「結構毛だらけ猫灰だらけ、お尻の周りはクソだらけってねぇ。タコはイボイボ、ニワトリゃハタチ、イモ虫ゃ十九で嫁に行くときた。 黒い黒いは何見て分かる。色が黒くて貰い手なけりゃ、山のカラスは後家ばかり。ねぇ。色が黒くて食いつきたいが、あたしゃ入れ歯で歯が立たないよときやがった!。」
映画「男はつらいよ」車寅次郎の口上の一節より
映画「男はつらいよ」で寅さん(渥美清)の口上で昭和の人々の耳に馴染み深い結構毛だらけ猫灰だらけ。でも不思議なのが「結構毛だらけ猫灰だらけ」の猫ちゃん。何故、猫が灰だらけになっているのでしょうか?。
それは、猫がかつて灰だらけになっていたから。猫が自ら灰だらけを望んだからに他なりません。かまどでご飯を炊いていた頃、日本では灰だらけになった猫が当たり前に見られたのです。
猫灰だらけと俳句の世界

「結構毛だらけ猫灰だらけ」は、「結構です。(不要です)」という場合に使われました。言葉の意味は違うのだけれど、当たり前の事を「あたり前田のクラッカー」というおやじギャグのようなものとご理解ください。今なら「モチのローン」という所でしょうか?。
そこで気になるのが灰だらけになった猫ちゃん。
灰にまみれた猫なんて見た事ありませんよね?。猫が家に住んでいる僕もその一人。そもそも『灰』を見る機会なんて炉端焼きを食べに行った時くらいです。
では、どうして猫が灰だらけにならなければならない理由があったのでしょうか?。それは、竈猫(かまどねこ)という言葉の意味を知れば理解出来ます。

竈猫とは、俳句で使われる冬の季語です
現在のようにストーブやエアコンなどが無かった時代。冬の寒さから身を守るために、猫は竈(かまど)の灰の中に潜ったりしたそうです。竈に火が着いている間は、暖かい竈の前で暖を取り、やがて竈の火が消えると、猫は暖かさの残った灰の中に潜り込んでいたそうなのです。その姿はまさに「猫灰だらけ」。
何もかも知つてをるなり竈猫
富安風生
火を落とした後の暖かい竈の灰の上で丸まっている猫の姿を見て、富安風生が読んだ一句。

家での出来事、良い事も、悪い事も、嫁の愚痴、姑の愚痴、知りたい事も、知りたく無い事も…。
何もかも、全てを知った上で、知らぬふりをして寝ている猫を想った俳句です。この一句で「竈猫」は冬の季題として定着したと言われています。ちなみに猫を季語にした俳句は多く、
- 恋猫
- 猫の妻
- 猫の夫
- 浮かれ猫
- 猫さかる
- 通ふ猫
- 子持猫
- 子猫
などは春の季語です。

愛猫サヨリも今年で15歳。来年も再来年も一緒に桜をみてやりたいと思います。

最後に『キジとら』からのお知らせです

今のおすすめ記事は『ユニクロのヒートテック2021が暑い!』デス❤

最後まで読んで頂きありがとうございました。毎日、頑張って更新しています。よろしければお気に入りの片隅にこっそりご登録して頂ければ幸いです。ブログもよろしくお願いします。
『キジとら』は昭和感満載の雑記ブログです。ノスタルジックな言い回しが多数出現しますが暖かい目で見守って頂ければ幸いです。無駄に記事数だけは多いので暇つぶしには最適ですよ、たぶん…(笑)

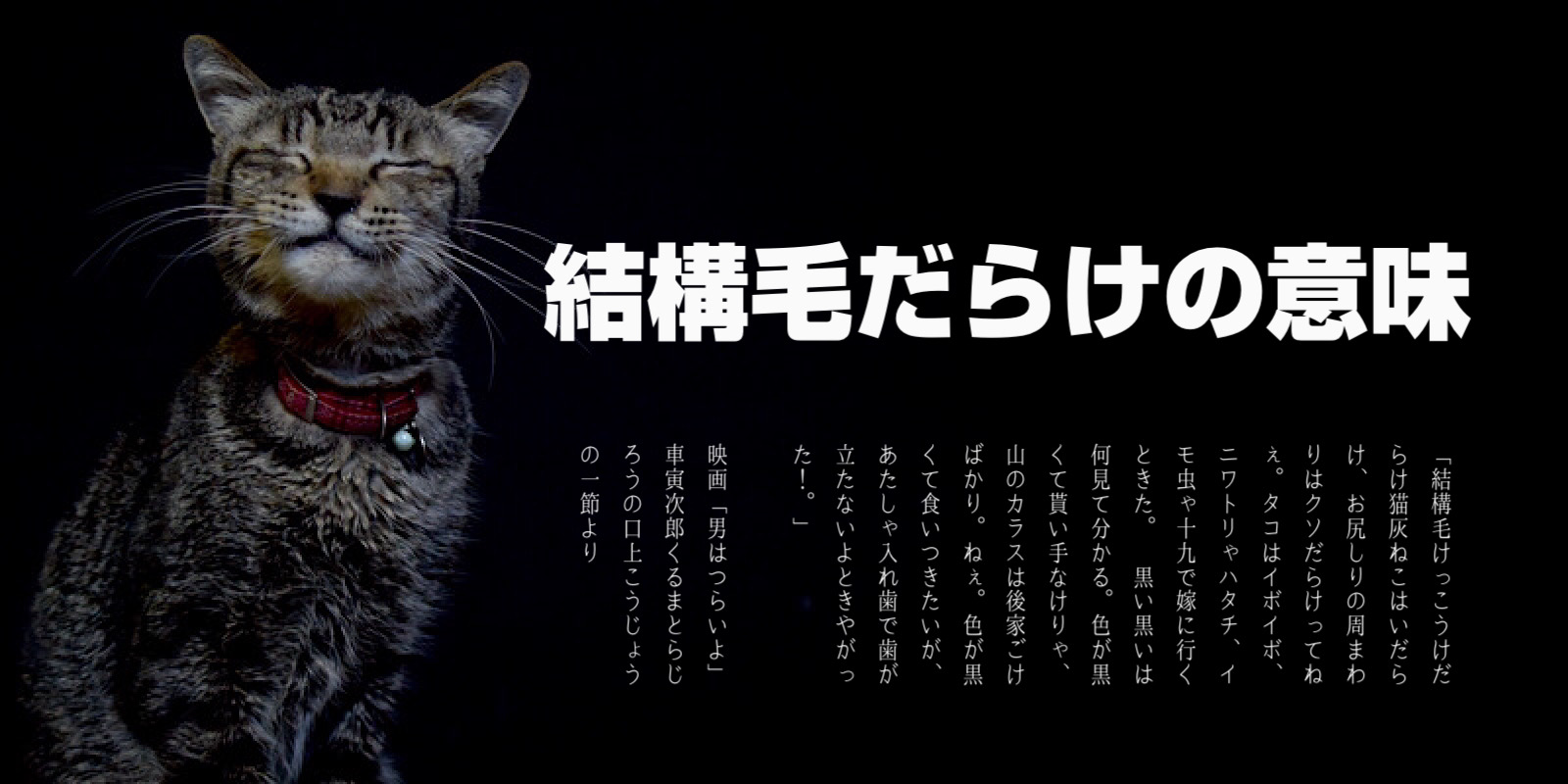

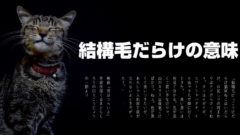



Related Posts