───家を出から3分歩けば海だった。
スマホもファミコンも無かった時代。暇、暇、暇。ブラウン管から流れる2時のワイドショーに我慢の限界が越えた。
───うん、つまんねー。
白いジャイアンツの野球帽を被り、針と糸とスコップを持って家を出る。魚を釣るための針と糸。餌を取るためのスコップだ。
運命の赤い糸。縦の糸はあなた、横の糸はわたし、そんな、気の利いた発想など小学生にあるはずもなく、獲物を求めて海に出る。本能のままにゴカイ(餌)のいそうな海辺の大きな石をひっくり返す。
───1個、2個、3個。
おった。
魚の餌を5、6本仕入れたら、いつもの港へと足を運ぶ。昭和50年、当時の瀬戸内は堤防の上からでも海底が見えた。海底の砂に隠れるコチやハゼですら裸眼から確認できた。アジやイワシは雑魚の部類だ。
───カレイやヒラメは滅多に見なかったけれど。
それが僕らの当たり前で日常だった。僕の仕事は針に餌をつけて魚の目の前に針を落とすだけ。それだけで面白いように魚が釣れた。
岩場では魚の種類が一気に増える。
───ベラ、アイナメ、ガシラ、タコ、ワタリガニ。
今、スーパーで結構なお値段の魚介類も、僕らには雑魚だった。魚は釣れて当たり前。そんな世界が目の前に広がっていた。
それを他所目に大人達は高級そうな竿とリールを使い、ロケットと呼ばれるオモリを使ってビュンビュンと針を海へ飛ばしていた。円盤と呼ばれるオモリも存在してたけれど、時代は弾頭の赤いロケットが主流だった。
───いつかはロケット。
そう思いながら目の前の獲物を釣り上げる。ブルブルと糸から伝わる振動が心地良かった。小さな魚はカニ釣りの餌。大きな魚は晩御飯。
───家には青色のタンクがあった。
その中にはいつも新鮮な海水が入っていて、釣れた魚をストックする生け簀の役割を果たしていた。つまり、獲物は生かして帰るシステム。元々は、拾った貝の潮吹き用として父が買って来たものだ。シーズンに入ると、ハマグリ、アサリ、サザエ、バカ貝、何かしらの貝が潮を吹いていた。
毎日ように海に出ると大人達とも仲良くなる。カレイ、ヒラメ、たまに鯛。大人がリール巻き始めると、子供らは周りに集まり糸の先に全集中。何が出るかな、何が出るかな?。スマホガチャのような感覚で糸の先に期待した。
大物が上がれば歓喜し小さければガッカリ。リールの音がするまで足元の魚を釣り上げる。リールが回ると全員集合。その繰り返し。金にも勉強にもならない。そんな単調で贅沢な時間だけがその場を支配し続けた。
大人の悪戯、夜の堤防で怪談話
夏休みは夜釣りの季節である。単1電池が6個も入る大きな懐中電灯を持って堤防へ向かう。空に向けると光の棒が天に昇る。それだけでワクワクだった。子供だけの夜の集会。今なら育児放棄、幼児虐待などと呼ばれるだろうが、あちら側では馴染みの大人達が夜釣りに熱狂していた。
───そこで毎回、海の怖さを教えられるのである。
夜の海は恐ろしい。
それは教えられるものでもなく直接肌身に感じていた。とりあえず落ちたら死にます。それだけを理解していた。午後8時を回れば、おじさんらから、「帰れ!帰れ!」と急かされる。それでも帰る道理がない。
───夏休みだもの。
そこから大人の悪戯が始まる。怖がらせて帰らせる作戦に出る。
「おまえら、面白い話をしてやろうか?」
知ってる、それ嘘でしょ。
全員が集まり、オジサンの、、、いや、いや。お兄さんだったかな?。お兄さんの話に耳を傾ける。もうね、釣り糸そっちのけでノリノリだ。
───話の内容は海の怪談。
それはいつもの事で決まっているのに、僕らは何故か話を訊いてしまう。だってそうでしょう?、同じ話が無いのだから。毎回、新作を発表するのだから訊いてしまって当たり前だ。
───お昼のワイドショーよりも面白い。
世は、エクソシストで端を発した第一次ホラーブームの真っ只中。オーメン、キャリー、あなたの知らない世界。生温い夏の風、波の音さえお兄さんは味方に付けて話を進める。
怖いなぁ〜、いやだなぁ〜、気持ち悪いなぁ〜、この世のものじゃない!。稲川淳二さながらの新作をドキドキしながら聴いていた。1話あたり5分とか10分のショートショートなお話だ。海から手が出てきたとか、海に引きずり込まれたとか、海に放り込まれたとか、そんな定番のお話だったけれど、雰囲気がね、夜の海だもの。
───僕らは黙って話を聞く。
話のパターンは決まっていた。マクラは様々だったけれど、最後は決まって、懐中電灯を顎元から照らして僕らを脅かす。今思えば、子供を怖がらせるのがメチャクチャ楽しかったのだろう。懐中電灯の灯りに照らされた顔は、いつも慢心の笑顔だった。
───笑顔が一番恐ろしい。
ギャ───!。
っと叫んでから、僕らはいそいそと帰り支度を始める。まんまと大人の策にはまる。大慌てで片付けをし、大急ぎで帰路についた。
この話には続きがあって、港からの帰り道が最も怖い。というのも、帰り道には墓地があり、全員が墓地を避けて帰れないのである。街灯も無く懐中電灯の灯りだけが頼り。どうしても墓石にライトが当たってしまう。数分間の怖さに怪談がミックスされて、恐怖が指数関数的に高まる。
そんな時に、誰かの親が迎えに来るものだから堪らない。ライトが照らした顔はいつも鬼の形相だった。
───悪かった、悪かった、お前ら馬鹿なの忘れてた。
昭和の小学生は学習などしない。つまり、懲りない。僕らは何度もその策にはまり続けた。僕らは決してくじけない。翌日になると、すっかりさっぱり怪談話など忘れて堤防で釣り糸を垂れていた。
───子供を持つ歳になって思う。
あのお兄さんが、毎日、毎日、夜釣りに来ていたのは、僕らを事故から守るためだったのだろう。愛の鞭と言うやつだ。存命なら80歳を越える年齢である。もう一度、何処かで逢えたら昔話に花を添えて、何かしらのお礼がしたいと切に思う。
それは、大らかだった遠い昔のお話。






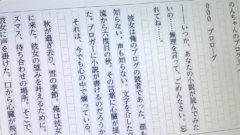
Related Posts