男の人が泣いていた……心の奥底から何もかもが湧き出るような涙だった。
幼き俺は、号泣する大人を初めて見た。その涙は、悲しいでもなく、うれしいでもなく。人が抱く感情すべてを、何層にも折り重ねたような涙に見えた。フィユタージュの涙を流しながら、俺の隣で泣き崩れた人。それは、俺の父親……オトンであった。
ばあちゃんが言っていた。
───あの人が本気を出したら凄いのよ……。
じいちゃんの部屋にある古びたギター。弦の隙間にピンクのピック。それが、アンバランスさを醸しだす。そのギターの音色を俺は知らない。鼻歌混じりで畑仕事。そんな、陽気なじいちゃんだけれど、本当の歌声すら俺は知らない。ギターがあるのにじいちゃんは歌わない……俺にはそれが不思議だった。
「じいちゃん、ギター弾かないの?」
幼き俺は問いかける。ばあちゃんに問いかけた。
ばあちゃんは、元々、関東の人間だ。だから、話す言葉が讃岐弁とは全然違う。ばあちゃんの口から出る言葉は、時代劇の芸者さんのような口調だった。
「あら、嫌だねぇ~。わたしのイチロさんは、ギターも歌も上手いんだ。心に響くってのはね。あんなのを言うんだろうねぇ」
じいちゃんは上手いのか。だったら、どんな何を歌うのか?
「じいちゃんは、何を歌う?」
俺がじいちゃんの話題をすると、ばあちゃんはいつもうれしそうだ。だから、ばあちゃんは、俺の理想の花嫁像であった。どんなときも、いつだって。ばあちゃんは、じいちゃんファーストで生きてきた。たとえ生まれ変わっても、ばあちゃんはじいちゃんだけを選ぶだろう。ふたりの馴れ初めを知らぬ俺は、絶対そうだと信じていた。
ばあちゃんは、自慢げに話を続ける。
「さだまさしとかぐや姫。三縁さんは、知らない歌ばかりだね。遠い昔の流行り歌だよ。イチロさん。若いころは、よく歌ってたねぇ。今じゃ、年に1度だけになっちまったけど。でも、歌うよ。今でも歌っているよ。上手にね、ギターを鳴らして歌うんだ。グレープの精霊流し……知らないよねぇ。でも、イチロさんの歌、聞きたいかい?」
ばあちゃんは、分け隔てなく誰にでも〝さん〟の敬称を付けて呼ぶ。ツクヨに対しても、キチンと月読さんと呼んでいる。それは凄いことだと俺は思う。だって、大人はいつも偉そうだから。
じいちゃんの名前は飛川一郎。ばあちゃんは、愛情を込めて〝イチロさん〟と呼んでいる。いつだって、イチロさんの前に〝わたしの〟の冠を乗せている。
ツクヨの〝わたしのオッツー〟は、ばあちゃんの真似をしているのだろう。でもどうして、オッツーだけが呼び捨てにされるのかは謎だけど……。
「うん」
「そうかい、そうかい。イチロさんの歌が聞きたいかい? うれしいことを言ってくれるじゃないの。わたしのイチロさんは最高だからね。わたしだって、キュンキュンしちゃうよ」
永遠のデレデレだ。そのデレデレに、ツンの要素がまるでない。その後で、ばあちゃんが俺に言う。
「でもね、ギターに触れてはいけないよ。あのギターはね、イチロさんの宝物だからさ。わたしのイチロさんが大切な人から受け継いだものさ。小さな三縁さんにゃ、分からないだろうけどね。だから、よーくお聞き」
少し真顔で……それは、俺への警告だった。
「うん……」
「お前のじいちゃんの大切な人は、もう、この世にはいない。あのギターの代わりはないのさ。だから、ギターに触れてはいけないよ。もし、指一本でも触れたなら、可愛い孫でもタダじゃおかないからね! 分かったかい?」
「う……うん……」
ばあちゃんに先手を打たれた。
ギターに興味を示した幼き俺へ、ばあちゃんからの防衛ライン。今の俺なら理解出来る。あれは、さくらさんのギターなのだと。じいちゃんに恋をして、じいちゃんも恋をして。じいちゃんと逢えぬまま、さくらさんはこの世を去った。それは、ブログ王に書いたとおり。さくらさんの死によって、じいちゃんは小説を書きあげたのだ。そして、その裏では……。
「でもね、だったらね、じいちゃんの歌はいつ聞ける? カラオケ行こうよ、カラオケ、カラオケ!」
ばあちゃんのニヤニヤが止まらない。その口ぶりは、推しのアイドルでも語るようだ。じいちゃんの団扇とか、こっそり作って持ってるタイプだ。
「そうだねぇ、三縁さんか文香さんの結婚式なら歌うかもしれないねぇ。となると……文香さんの結婚式が先だろうね。あの子、モデルみたいに美人だから。男が放っちゃおかないよ」
容姿抜群、スタイル抜群。事実、全盛期のアヤ姉はモテモテだった───誰もが認める美の無双だった。
「俺は?」
これは、俺として当然の質問だ。
「三縁さんは、が・ん・ば・れ(笑)」
目を細めてばあちゃんは、俺の頭をやさしく撫でた───俺の心が軽く折れた……。
そして今。ばあちゃんの視線の先で、じいちゃんをスポットライトが照らしている。それは、披露宴の演出である。ここから先は、アヤ姉の結婚式披露宴での出来事だ。
今日は、アヤ姉の晴れの舞台。
美の無双が純白のウエディングドレスに身を包む。その神々しさたるや、新婦入場で式場がざわめきで揺れたほどである。我が姉とは思えないほどの美しさ。同じ屋根の下で生活を共にした、弟の俺ですら見惚れてしまう。その結婚式に、ギターを持ったじいちゃんが登場したのだ。ギターを持ったいちゃんに、俺は少しだけワクワクし、じいちゃんの歌に期待を寄せた。
───おばあちゃんは夕餉の片づけを終……♪
さくらさんのピンクのピックが弦を弾くと、静かにギターが音を奏でる。それに、じいちゃんの声が乗る。すると、披露宴会場が静寂に包まれた。静寂に飲まれたと言うべきか。
アヤ姉は抜きんでたビジュアルで会場を魅了した。じいちゃんは圧倒的な歌声で会場を支配する───共に化け物だなと俺は思った。
ゆっくとした静かでやさしいメロディーに、じいちゃんのハスキーボイスが重なるだけで、ざわざわしていた会場から全てのノイズが消え失せる。
じいちゃんの口から羽ばたいた、言葉のひとつひとつが平仮名となって、幼き俺の耳にも届く。すると、どこかの家の情景が、俺の脳裏にポカリと浮ぶ。映画でも観ているかのように、魔法でもかけられたかのように、半ば強制的に思い浮かぶのが不思議だった。
赤ちゃんが産まれて、家族で女の子の成長を見守る歌詞が並ぶ。じいちゃんの歌声にオトンも耳を傾ける。ちびりちびりと好きな酒を飲みながら、時折、真っ赤な顔がくすりと笑った。それを見て俺も笑った。
女の子は、歌詞の中でゆっくりと成長を続ける。七五三、入学式、赤いランドセル、学級対抗リレー……学芸会の頃になって異変が起こる。
じいちゃんの歌声には、人を惹きつける何かがあるのだろうか?……どこからか、じいちゃんの噂を聞きつけた数名のフロント係とコックさんが会場を覗きにきたのだ。
───恐るべしはじいちゃんだった。
初恋、高2、バレー部キャプテン……。物語でも語るように、じいちゃんは歌い上げる。すると、徐々に俺の隣で起こる異変。オトンの挙動が怪しくなった。
オトンが壊れる5秒前……。
つまり、じいちゃんが歌い始めて8分39秒後。ついにオトンが壊れてしまう。壊れた蛇口のように涙腺が崩壊したのだ。オカンと親戚のみならず、オトンの席に友人までもが駆け寄った。会場の視線がオトンに集中する中でも、構わずじいちゃんは歌い続ける───じいちゃん……あなたはプロですか? これがプロ根性というやつですか?
それから先は見てられない。オトンの理性は崩れる一方。幼き俺の目から見ても、目、鼻、口。顔のパーツ全てから謎の液体が流れている。酒で焼けた赤い顔。それが、ボロボロでズタズタになった。
おしぼりから始まったのに、歌の終わりはバスタオル。しばらくの間、オトンの顔はバスタオルで覆われていた。〝余儀なく退場〟それすら俺は予感した。子ども心に俺は思う───これが、じいちゃんが歌わない理由なのだと。
とはいえ、オトンが泣くのは当然である。これで泣かない父親などいない。ところが、歌が終わって会場内を見渡せば、ほぼ全員が泣いていた。そして始まるスタンディング・オベーション───もう、じいちゃんから目が離せない。若きイケメンウエイターまでもが拍手しなから、おしぼりで目頭を押さえている。
その光景を満足げな瞳で眺めているのがばあちゃんだった。感動も突き抜ければ恐怖である。ふたりが歌の魔王と魔女のように、その時の俺には見えていた。
この会場で冷静を保てたのは、俺のようなお子ちゃまと、じいちゃん大好きばあちゃんくらいのものである。
いつになるのか分からない。でも、じいちゃん。俺の結婚式でも歌ってくれるよな? 俺の隣の花嫁が、カノンであることを切に祈る!
幼き俺はこっそりと、ばあちゃんに耳元で囁いた。
「あの歌って、何て曲?」
ばあちゃんは、幸せの絶頂期のような笑顔で俺に答えた。
「親父の一番長い日よっ!(笑)」
今日のオトンそのものだった。

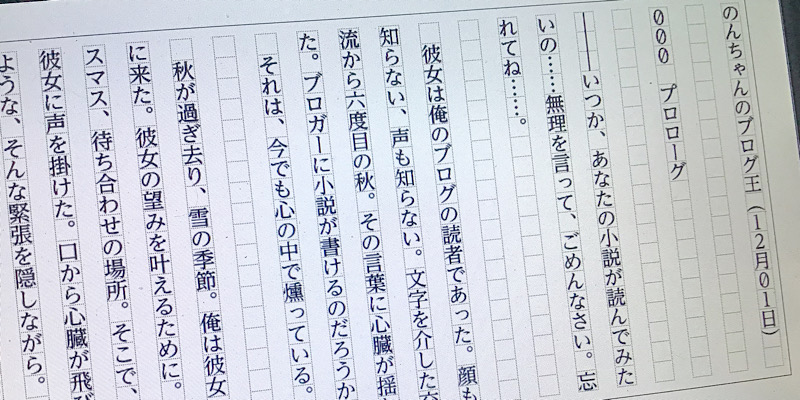
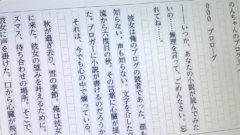
コメント