のんと楽しいクリスマスを過ごした翌年。地元大学への入学切符を手に入れた俺の元へ、青葉導人と名乗る人物から手紙が届いた。俺は思った───詐欺かもしれない。とてもじゃないけど、こんなの俺の手に負えない。だから、次の一手は決まってる! 桜木だ。俺は手紙を手に持って、ゲンちゃんうどんに桜木を誘った。この手紙が、俺の人生のターニングポイントになるとも知らずに……。
「ごめんな……桜木、上京の準備で忙しいところ。こんな手紙が来たんだけど……俺、バカだから手に負えなくて……」
桜木が俺宛の手紙に目をとおすと、ぱっと表情が明るくなった。
「こんな手がありましたか……」
明るい顔で意味深な言葉を口ずさむ。
「なんだよ、桜木。その手って?」
俺には何が何だか分からない。
「この手紙は、作家デビューへの架け橋ですよ」
作家デビュー? 架け橋? 余計に俺は混乱した。
「てか、誰の? てか、誰が?」
「決まっているでしょ? 飛川君、あなたのですよ。去年、旅乃琴里宛に〝ブログ王〟を送りましたよね? それが、旅乃琴里の担当さんの目に留まって、社内を回ったのでしょう。そして、あなたに興味を持った人物がいた……それが青葉さん。ですが、作家デビューは容易ではありません。デビューにコネも裏口入学もありません。そもそも、社員の一存ではどうにもなりません。だから、新人賞に応募するよう提案されたのです。これなら正々堂々、書籍化可能ですからね。青葉さんは、余程、飛川君が気に入ったようですね」
そう言い終わると、桜木はメガネの奥の目を細めた。自分のことのように嬉しげなのだが、やっぱり困惑している俺がいた。プロ作家? 俺には、それがイメージできない。
「はぁ? 無理、無理、無理、無理。だってそうだろ? 俺、小説家になる気もなければ、小説の書き方なんて忘れちまった。もう、書けないよ……小説なんて」
ブログ王は、花音のために書いたのだ。その先なんて考えてもいない。それで終わりのつもりだった。俺はブロガーなのだから。トレイの上のうどんを見つめながら、沈黙する俺がいると───俺の意識が一瞬、飛んだ。何者かの手によって、後頭部に強烈なダメージを受けたのだ。痛いというより飛ぶって感じだ。
「うぉっ!!!!! だ、誰だよ?! 記憶喪失になったら、どうしてくれんだ!!」
「ねぇ、アンタ。覚えてるぅ? 私だよっ!」
空のトレイを持ったアケミが俺の横に座り込む。ふたり分のうどんを持って、ゆきは桜木の横に座った。アケミは肉(大)で、ゆきはざる(小)。咄嗟にそう判断してしまうのも、讃岐人の嵯峨である。てか、アケミはいっつも大(二玉)だよなぁ……。
「アンタ、さっさと応募しなさいよ! こんな大チャンスなんてね! それこそ、小説の世界でしかないわよ。小説家になっちゃいな! 私としてはね、少し複雑だけど……あぁ! イライラする。どうして、世の中は不公平なのよっ!」
イラつくアケミの気持ちは分かる。アケミだって小説家になりたいのだ。俺なんかよりもずっと、ずっと……。
「そうよねぇ。小説家になりたいのは、アケミちゃんなのにね。だからこそサヨちゃんは、応募すべきだとわたしも思うの。ねぇ、やってみたら?」
ゆきはアケミの意見に賛同した。
「飛川君。こんなチャンス、人生で何度もありませんよ。アケミさんのように、小説家になりたい人たちは、何万人も存在します。その中でチャンスをつかめるのは一握り。大学生のうちにやってみて、自分に合わないと判断すれば、就職すればよいのでは? 僕も、そちらのおふたりも、今とても嬉しいのですよ。とてもとても、あなたを誇りに思っています。それを誰よりも喜んでくれるのが……のん……花音さんですよね? そしてもうひとつ。旅乃琴里に直接会って、ポメラのお礼が言えるかもしれませんよ。だって青葉さんは、彼女と同じ出版社の社員さんなのだから」
花音が喜ぶ? 旅乃琴里にお礼が言える? だったら、やろう!
若さとは単純だった。俺がバカなだけなのだけれど。俺は青葉導人に指示された新人賞に応募した。そしてめでたく入選を果たしてしまった。大学生と小説家。俺は二足のわらじを履くことになった。そして、青葉導人が俺の担当者になった。今思えば、全てが青葉導人の思惑どおりだったのかもしれない。
その年の夏。作家デビューを果たした俺は、いつもの堤防で釣り糸を垂れていた。堤防に座り込んでウキを眺める。そうやって、次作の構想を練っていた。
「そこで釣りに勤しんでいる若者は……飛川三縁先生……かな?」
ひょろっとした三十過ぎの男が俺に声をかけた。黒いスーツを着ているけれど、ボサボサ頭に無精ひげ。どう見たって堅気じゃないな。俺のアンテナが危険意人物だと判断している。でも、この男。どこかで見た気もするのだけれど……。
「えぇ……飛川ですけど、先生ではありません。人違いだと思います」
そう言って、俺はウキに目を戻す。
「リアル世界では初めまして。青葉導人です。ちょっと讃岐うどんが食べたくなりましてねぇ、ついでにお顔を拝見に伺いました」
ついでなのか……。とはいえ、キチンとお礼を言わねばならないな。俺は堤防のふもとに竿を置き、彼に向かって頭を下げた。
「その節はありがとうございました。おかげで小説家になることができました。てか、テレワークの青葉さんって、アバターですか?」
「あぁ、アレね。びっくりした? ちょっ~とだけ盛ってるよ。でも、最近の技術は凄いよねぇ~。僕も若い先生相手に楽しくなっちゃってね……」
にしても……盛り過ぎじゃん? この日から、俺の小説家としての修業が始まる。彼は俺を先生と呼び、俺は彼を師匠と呼んだ。
「おやおや、先生に師匠と呼ばれるのはチョットなのですけどねぇ……」
「だったら、先生ってのを止めてくれたら考えますよ、青葉師匠」
そんな先輩後輩のような関係が、画面越しに4年間続いた。けれど、一度も旅乃琴里と会えるチャンスには恵まれなかった。鉄壁のガードは健在だった。大学卒業と共に、俺の担当者は交代した。風の噂で師匠は、新たな新人発掘をしているらしい。デビューしてから10年後───再び師匠が俺の前に現れた。
「おやおや……こんなところまでお珍しいことで───青葉師匠(笑)」
「いやぁ~ねぇ。ちょっと讃岐うどんが食べたくなってねぇ~───飛川先生(笑)」
彼は新たな人材を見つけたようだ、俺を見つけた時のように。俺だって、いつまでもガキじゃない。それは、嵐の前の静けさだった。俺は師匠の腹の内を探り始める。
「にゃははははは……こいつはスクープですわよ、忍ちゃん!」
俺と師匠との会話を盗み聞いていたのが、師匠を案内してきたツクヨである。大学生になったツクヨと忍をも巻き込んで、俺たち放課後クラブが再起動する……のか?

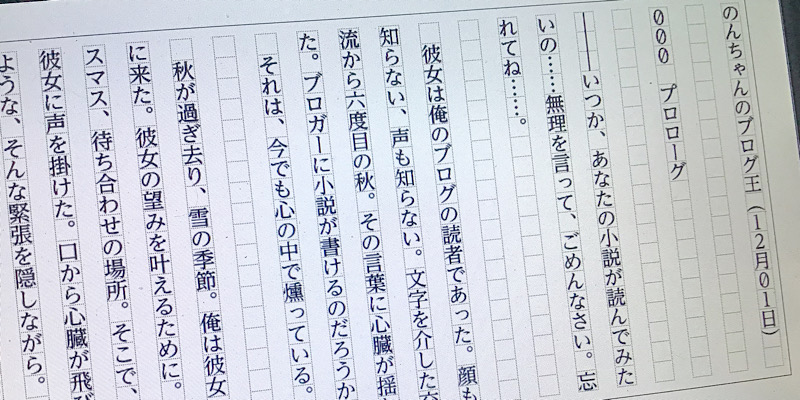
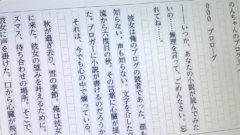
コメント