今日は、全国的にバレンタインの前日だった。
都会ではデパ地下が揺れる日らしい。けれど、こっちじゃマルナカがざわつく程度のことである。そして、俺にもオッツーにも無縁の日なのだからどうでもいい。
俺たちにチョコをくれるのはゆきだけである。毎年ゆきは、1粒だけチョコをくれる。ジャン=ポール・エヴァンのバレンタイン限定チョコだ。ゆきがパパに渡すついでに同じのをもう一箱買うのだ。それを、ママと一緒に食べている。俺たちのチョコはおこぼれである。だがしかし、これは、貴重なおこぼれだ。
「はい、お・す・そ・義理♡ 先生に見つからないでね」
バレンタインの朝。そう言って、ゆきはチョコを渡すのだ。義理とはいえ、1個とはいえ、このチョコ1粒600円。こんなの一生かけても貰えねぇ。だから、三回まわってワンの勢いで、俺たちはチョコを受け取っていた。バレンタインも〝ゆき〟を〝ゆき様〟と呼ぶ日である。
そのバレンタイン前日。
放課後、アケミとゆきに詰め寄られるオッツーがいた。発端はツクヨである。ツクヨは、数日前から俺にオッツーの話ばかりをするようになった。
「サヨちゃん、オッツーなにかいってない?」
「何を?」
「なんでもない……」
これが何度も繰り返される。さすがの俺も気になってアケミに相談。すると突然、アケミ爆発! それが、ゆきに飛び火したのだ。どうしてそうなるのか、俺たちにはさっぱりだ。ただ、アケミの地雷を踏んだのは、揺るがない事実であった。
「オッツー、ちょっと、ここにお座り」
オッツーは犬ですか?
アケミの眉間にシワが寄る。訳も分からず椅子に腰かけるオッツー。教室の机を挟んで、アケミとゆきは真正面に座る。さながら、刑事ドラマのワンシーンだ。
「オッツー! ツクヨちゃんのお土産に何をもらったって?」
アケミのトーンは〝犯人はお前だっ!〟って感じである。きっと、白でも黒にしてしまうのだろう。
「富士山アポロ……でした……」
「富士山アポロをどうしたって?」
アケミの追求は止まらない。
「サヨっちと食べた……」
「何ですって!」
キッとした目でアケミが俺を睨んでいる。ゆきは蔑んだような目で俺を見ている。オッツーよ、俺の名前を出すんじゃない。俺はギョッとして目を伏せた。
「ねぇ、オッツー。富士山アポロって、何で出来てる?」
アケミのトーンが和らいだ。怖い刑事の次は優しい刑事。そのうち、カツ丼が出そうである。
「チョコレートだけど……それが何か?」
「あっ!」
とっさに俺の口から声が出た。
気づいてしまったのは俺だった。そっか、そっか、そういうことか……。だから、わたしのオッツーか……そんでもって忍ちゃんか……俺は妙に納得した。
「それは、罪づくりですね(笑)」
俺の背中越しから声がする。声の主は桜木だった。
「桜木。いつから、そこにいたの?」
「最初からです。ここで本を読んでいましたよ。ここは僕のクラスの教室ですし、あなた方が入ってきたのですよ。アケミさんも、ゆきさんも、僕に気づいていたと思いますが……」
「そうなん?」
確認である。報告・連絡・相談。何事も、ホウレンソウは大切なのだ。
「うん」
アケミとゆきは頷いた。かわいそうなのは、オッツーである。ずっと、オドオドしているのだ。正義の味方オッツーに、桜木が正義の味方に見えただろう。神にもすがる顔をしている。
「オ……オレ、どうしたらいい?」
オッツーが桜木に答えを求める。
「ツクヨちゃんに今度会ったら。『チョコレート美味しかったよ、ありがとう』それで十分ですよ」
「それだけでいい?」
「それだけで結構です(笑)」
桜木の笑顔にオッツーは胸を撫でおろし、桜木の代弁により女性陣の怒りも収まった。
「帰ったら、ツクヨちゃんに、それ、言ってあげなよ! アンタもチョコ食べたことは言っちゃダメよ!」
アケミが俺に釘を刺す。
「はい。わかりました……」
ゆきのチョコしか知らない俺たちに、そんなの分かるはずないのに……道端で、いきなりヤンキーにボコられた気分だ。何かが解せん。
「じゃ、話は終わったから、わたしたち帰るわね。ゆきちゃん、帰ろう」
アケミがゆきに声をかける。
「うん、帰ろう。明日、チョコ持ってくるね」
ゆきは小さく手を振った。
「じゃ、俺たちも退散、退散。桜木はどうする?」
今日は早く帰りたい。オッツーが喜んでいたとツクヨに話してあげないと。喜ぶ顔が目に浮かぶ。
「僕はもう少し本を読んでから帰ります。皆さんは、お先にどうぞ(笑)」
桜木は読書を再開。
「じゃ、また明日な」
「じゃ、またね」
そう言い残して、俺たちは教室を後にした。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
賑やかだった学校も、静まり返った夕暮れ時。
桜木は校舎の下駄箱の前に立っていた。
下駄箱へ紙袋を忍ばせながら彼は呟く……
「ほんとに……アナタって人は……」
下駄箱に貼られたネームは〝飛川〟であった。

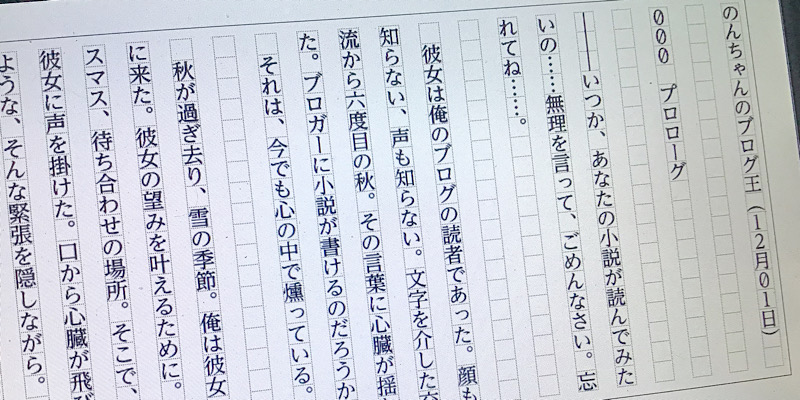
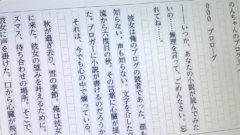
コメント