午前零時のダイニング。
ドアを開くとオトンがいた。ニヤニヤしながら、ひとり淋しく缶ビールを飲んでいる。酒のつまみはイカの足。テーブルの上に350mlの空き缶が二本あった。つまり、手にしているのが三本目。飲み過ぎだ……。
左手に持つスマホには、ツクヨの写真が表示されている。今年のハロウィン、仮面ライダー2号のコスプレ。ツクヨがオッツーの好みに合わせたのだろう。オッツーのベルトを腰に巻いて、ご満悦のよき笑顔である。オトンのスマホは、ツクヨちゃんの詰め合わせ。それを眺めて、夜遅くにニヤついていたというわけか……健気だ。
「まだ起きていたのか? 受験勉強、がんばれよ」
す、すまん……そうじゃないんだ。のんへの小説を書いているのだけれど、それはとても言えやしない。
「う……まぁ~ね」
スルメの足を咥えて、オトンはちびちびと缶ビールを飲んでいる。そこで会話が終わるのかと思いきや、今日のオトンはしつこかった。
「ところで三縁。彼女できたか?」
「え?」
「彼女だよ。か・の・じょ」
何、言ってんの? 酔ってんの?
「いねーし、そんなの」
「お姉ちゃんがお前くらいの年頃にゃぁ~、そりゃ、取っかえ引っかえだったのになぁ……。さてはお前、モテないの?」
何、言ってんの? 口の隙間からイカの足を出しちゃって、俺の自尊心を傷つけてんの? そんなの言葉の暴力じゃないか! オトンは申し訳なさそうな顔して話を続ける……。
「顔が俺に似たからかな? だったらぜんぶ……俺のせいだ。すまないな……こんなDNAでホントにごめん」
そんな目をして肩を落とさないでくれ……謝らないで、こっちが辛くなるから。オトンの言葉に、嫌われたらどうしよう。急に俺は、のんと会うのが怖くなった。本だけ作って郵送しようか……。酒の力で謎の進化を遂げたオトンの口が止まらない。
「アケミちゃんは美人だから、彼氏とかできたのか?」
舌の根の乾かぬうちに───オトンは男女交際から離れない。何だよ、何だよ、根ほり葉ほり……学生時代は、風紀委員でもやってたの?
「いねーよ」
「ゆきちゃんは?」
「いねーし」
「桜木君は?」
「おりません!」
「そっか……じゃ───仮面ライダーは?」
じゃ───って、何だよ?! そこはオッツーとか尾辻君とかでしょうに。まぁ、確かに仮面ライダーではあるけれど。
「俺の周りはボッチばかり。今年も淋しいクリスマスを迎えるのさ……ふふふふふ」
俺にはのんがいるけどな。とはいえ、ヨッパの相手などしてられない。俺はコーヒーを入れに来ただけなのだ。だがしかし、今夜のオトンは絡み酒。俺を手放す気などないらしい。会社の飲み会というのは、こんな感じなのかもしれないな……。
「なぁ、三縁」
ホラ来た。
「う?」
「仮面ライダー。ツクヨのこと、どう思っているのかな?」
「え?」
高校生と小学生との間に愛も恋もなかろうに……。心配にすら値しない。
「クリスマスとか、ツクヨはデートに誘われたりするのかな? 遊びに行ったりするのかな?」
「小学生相手に、そんなの断じてありません! オッツーは常識人だ」
俺の断言に、オトンの顔が和らいだ。
「そうだよなぁ~。仮面ライダーは高校生だもんなぁ~。小学生なんて相手にしないよなぁ~───でも、ツクヨは可愛いぞ! ほらアレだ……ツクヨは美少女さんだぞ! そしてワシは、断じてアイツをオッツーなどとは呼ばんからなっ!」
どうして、そこから離れない? 俺の親友を何だと思ってる? てか、何で少しキレてんの?
「だってほら。わたしのオッツー、わたしのオッツーって。ことあるごとに、仮面ライダーの話ばかりじゃないか。俺はね、心配なの。孫がね、可愛いから」
背中を丸め、オトンは缶に向かって語りかける。そこは、こっち向いて言うセリフだろ? はっはーん、ジェラシーか? そうなのか? そうなんだな? 高校生相手にオトンは嫉妬してんだな?
「大丈夫やで、大丈夫。あのふたりは気の合う仲間。だったらクリスマスに、ツクヨを誘って遊びに行けば? おもちゃでも買えば喜ぶで」
まぁ俺は、のんの所へ行くけどな。
「そうだなぁ、誘っちゃおうかなぁ~。お前も一緒に行くか? 遊園地」
だから……俺は、のんの所へ行くんだよ。
「俺はほら、受験生だから遠慮しとくよ」
「そっか……残念だな」
オトンの顔は、まったく残念そうな顔じゃなかった。むしろ喜びの表情である。とてもビールが美味そうだ。
「俺も遊園地に行きたかったなぁ~。残念、残念……」
俺は当たり障りのない返事でその場をしのぐ。オトンは機嫌を取り戻し、ようやく開放の兆しが見えたところで、風呂上がりのオカンがやってきた。タイミングの悪さにガッカリだ。
「あら、楽しそうね。私も一本いただくわん」
そう言って、冷蔵庫からビールを取り出しグラスに注ぐと、腰に手を添え一気に飲み干した。その姿は銭湯で見かけるコーヒー牛乳そのものである。ギャル時代には、相当モテたらしいけど、かつての面影などどこにもない。風呂上がりのビールに頬を赤らめて、ご機嫌さんでオカンは言った。
「ところでさぁ~あ。オッツー君って、ツクヨちゃんのこと、どう思ってるのかな? 考えすぎだろうけれど。ツクヨちゃん、オッツー君を見る目がねぇ……乙女なのよ」
鼻の下に付けた泡がひげのよう。白ひげオカンの〝乙女なのよ〟に、オトンと交わした会話のすべて。それが、一瞬で振り出しに戻されて、俺の努力は泡と消えた。缶ビールを握ったオトンの右手が小刻みに揺れている。俺はすべてを諦めた。できたてのコーヒーを手に持って、ゆっくりとオトンの前に腰を下ろした……。
時折始まる家族会議。それは、ツクヨが泣きながら帰ってきた、22歳のあの日まで続くのである……。

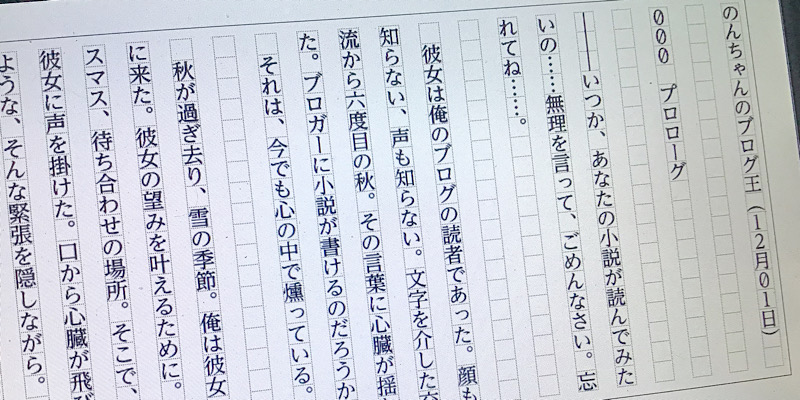
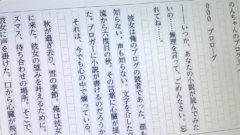
コメント