中二の春。
のんとゆいは、二年でも同じクラスになった。それは偶然なのか? それとも、不登校だったゆいへ学校側からの配慮なのか? それは誰にも分からない。けれど、のんと同じクラスにゆいはとても喜んだ。
「またウチら同じクラスだね。よろしくね、のんちゃん」
ゆいの笑顔が止まらない。
「ほんとだねぇ。よろしくねぇ、ゆいちゃん」
のんも目を細めて笑みを返す。
一学期最初の席順は出席番号順であった。視力が弱いのんの席は、いつもと同じく教壇の前である。休憩時間になると、ゆいはのんの席で話しをする。お昼はのんと一緒に弁当を食べる。このスタイルは中一時代と同じまま。それがゆいにはうれしくてたまらなかった。
昼食を済ませると、のんは必ずガラケーを開く。そして、カブトムシのブログを読んだ。このライフスタイルも変わらない。ゆいの記憶が正しければ、カブトムシのブログは夜八時に更新されるのだが……。
「のんちゃん。どうして何度も同じ記事を読んでるの? そりゃ、好きなのはわかるけど、目の前にウチがいるに……」
つまり、読んでいるはずの記事を、お昼休みに読み返しているのだ。ゆいにはそれが面白くなかった。一緒のときくらい、自分に集中してほしい。
「あ、ごめんねぇ。10秒だけ待ってねぇ」
「うん……」
心の中で、ゆいは数を数えた。1、2、3……10まで数え終えると、のんはガラケーを閉じた。
「ねぇ、のんちゃん。聞いてもい~い?」
「いーよぉ~」
ゆいは疑問をのんにぶつけた。それは、今回が初めてではなかった。この質問は、定期的に行われる意識調査のようなものである。
「ずっと気になってたけど、アイツのブログの何処がいいの?」
毎日更新されている以外、とりわけて特別なことなど書かれてはいない。なのに何度も読み返す、のんの行動が不可解なのだ。たとえ、カブトムシに恋愛感情が芽生えたとしても、その執着っぷりが健気に思えた。
「キュンキュンするの」
そう言うと、のんは頬を赤らめた。そのしぐさを見るたびに、ゆいはいつも思う。きゃぁ、可愛い! この子をカバンに入れて持って帰りたいと。それと同時に、カブトムシへの嫉妬心が、メラメラと燃え上がるのを感じていた。それはまさに、仮想敵国カブトムシであった。
「キュンキュンって……何処が?」
ゆいにとって、それは至極当然の質問である。ゆいはカブトムシにキュンキュンしないのだ。
「カブトムシさんのブログはね。ぜーんぶ、まとめてひとつなの。過去の記事が伏線なの。ある日、突然回収するの。それに気づく読者はねぇ。わたしだけかもしれないけれど、それでいいの。それがいいの。好きだから……」
次は耳まで赤らめて、のんはゆいにつむじを見せた。カブトムシの話題になると、いつもこうなってしまう。のんの反応にゆいはいつも困ってしまう。だから、取り繕うように話題を変える。けれど、今回は別の展開が待っていた。
「記事の向こう側に見えるの……」
ゆいの前のつむじが語り始めた。
「ん?」
ゆいは、のんのつむじを見つめている。
「ねぇ、ゆいちゃん。カブトムシさんって、いつも楽しそうでしょ?」
つむじがゆいに問う。
「そりゃ、まぁ……ゆーて、楽しそうではありますわなぁ」
ゆいが答えると、むくっとつむじが顔を上げた。
「でしょ? でしょ? 楽しそうでしょ? でもねぇ……違うの」
「え?」
ゆいには、のんの真意が理解できない。
「だれでも毎日、楽しいはずがないの。でも、それがわからないの。最後まで読んじゃうの。そんなふうに書いてるの。そこが凄いの。去年の記事が、今日の記事の伏線になってたりしているの。でも、それを書かないの。でねぇ……」
「でね?」
「それって、とても難しいの。カブトムシさんは無意識にそれをやっちゃうけど、その中にちょっとした寂しさを見つけると、そこにキュンキュンしちゃうの」
「キュンキュンねぇ……」
ゆいにはチンプンカンプンである。去年の記事を覚えている方がどうかしている。
「なんかねぇ~。小説も同じだけど、引き込まれたら書いている人が気になるの。だから、もっと彼のことが知りたくなるの。だから、何度も読み返しちゃうの」
ゆいは思った。のんはアイツの記事を一言一句、全て記憶しているのだろうと。
「そんなもんですかねぇ……あっ! それでコメントですか?」
おぼろげに、ゆいにも何かしらが見えてきた。
(そうか……だから、のんちゃんのコメントは、たまに大胆になっていたのか……うん、納得。だったらさ……)
勝手に納得すると、ゆいはのんに提案した。我ながらの妙案だ。ゆいは自信にあふれていた。
「だったらさ。毎日メールしちゃいなさいよ。もっと、アイツのことがわかると思うよ」
それは、ゆいの助言であり罠である。毎日メールでやり取りすれば、そうそう長くは続くまい。いずれ、アイツだってボロを出す。ゆいは心の中でほくそ笑むのだが……。
「わたし……毎日、メールしてるよ……」
「いぃ?……いつから?」
「ゆいちゃんに手伝ってもらって、最初にコメントした日の夜から……」
そう言うと、耳どころか指先まで真っ赤にして、のんは両手で顔を隠した。爪先がピンク色に染まって桜貝のように見えた。
(ま、ま、ま、ま、マジっすか?!)
これが決定打となり、ゆいの理性が崩壊した。
「うぉぉぉうぉぉ……ぉぉぉぉ!!!!」
ゆいは自分でも自分の声がおかしくなっているのが分かった。真っ赤な手のひらに隠れた口から、ゆいを案ずる声がする。
「ゆいちゃん、どうしたの? なんかねぇ……ホラ貝みたいになってるよ」
ゆい、人生初のホラ貝であった。

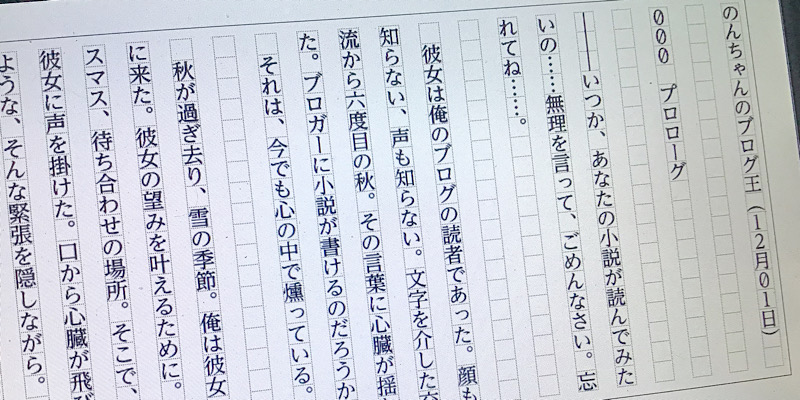
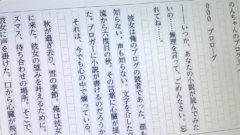
コメント