004 姉貴と姪っ子
───アヤ姉が家に帰ってきた……でも、何で?
何があったか知らんけど、姉貴殿が姪っ子を連れて出戻った。姉の名前は文香である。俺は物心ついたころから“アヤ姉”と呼んでいる。弟が言うのもアレだけれど、アヤ姉は美人である。
日本人離れした彫りの深い顔立ち。それに加えて、健康的な小麦色の肌とほっそりスリムなモデル体型。そんなアヤ姉を男どもが放っておくはずもない。幼いころ、俺は美人の恩恵を受けていた。
「ねぇ、ボク? キミは、文香さんの弟かい?」
「そだお(笑)」
「そっか、似てないね(笑)」
美人の弟は得である。おもちゃ、お菓子、アイスクリーム……。入れ替わり立ち替わり。家に知らないお兄さんが来るたびに、俺に何かをくれるのだ。幼き俺は理解する。美人と特権は同意語なのだと。『似てないね』その言葉に、引っ掛かるモノを感じながら……。
アヤ姉は、それほど魅力的な女性だった───もう一度言う。魅力的な女性であった。なのに、時の流れは残酷だ。だって、そうじゃん。ぽっちゃりにも限度がある。でも、今なら間に合う。だから、アヤ姉に俺は忠告したんだ。
「アヤ姉、ダイエットでもしたら? 最近さ、オカンと感じが似てきたんじゃね?」
それは、弟として当然の心配だった。弟としての気遣いだった。けれど、俺の一言が、アヤ姉の地雷を踏み抜いた。
「レディに対して失礼ね。そんなんだから、彼女のひとりもできないのよぉぉぉ!!!」
そう言って、俺は両親の前でぶん殴られた。あれからだ、その言葉が我が家の禁句になったのは。
アヤ姉と共に、我が家の一員となったのが姪っ子のツクヨである。月を読むと書いてツクヨ。この子が生を受けた夜。病室の窓から見える満月を、文字でも読むように見つめる赤ちゃん。だから、月読……よき名前だと俺は思う。
ツクヨは、おかっぱ頭で元気いっぱいの四歳児だ。肌の色はアヤ姉とは真逆で真っ白である。きっと、旦那さんの方に似たのだろう。そして、おしゃべりが大好き。いつも、家の誰かをつかまえて、あーだこーだと喋っている。きっと頭がよいのだろうな。言葉のチョイスに光るものがあった。
ツクヨが家に来てからというもの、パッと家の中が明るくなった。そして、オトンの不機嫌な顔もどこかに消えた。ツクヨは、オトンにとっては初孫である。きっと、目の中に入れても痛くないのだろう。ツクヨにはデレデレである。
でも、俺の心中は複雑だ。ツクヨは俺から見れば姪っ子である。ツクヨから見れば、俺は叔父さんなのだから。あの街角で、あの道端で、行きつけのコンビニで……同級生の目の前で。
「ねぇ、オジチャン(笑)」
ツクヨから、そう呼ばれると考えただけで、俺の背筋は凍てつくのだ。だってほら。俺って、まだ12歳だし……。せめて『にいちゃん』と呼んでくれっ! ツクヨに“サヨちゃん”と、呼ぶように教育したのは言うまでもない。
そんなツクヨが、妙に俺に懐いてしまった。俺の作ったデタラメ話。それに、ツクヨが飛びついたのだ。あれは、ツクヨと一緒に焼きいもを食べていた時だった。
「サヨちゃん、じいちゃんのおいも、おいしいね」
じいちゃんは、野菜作りが上手い。その中でもさつまいもは、格別に美味かった。大きな栗を食ってるような味と食感が癖になる。
「そうだろ? この、おいもさんは戦うんだぜ」
「なにと?」
「人参と。最初は弱いけど、焼くといもは強くなるんだ……」
こんな調子で、俺はツクヨに作り話をしてやった。暇つぶしのつもりで話した。
「おいもさんは、やくとつよくなるの?……すごい!」
いもは焼くと強くなる。その設定が、幼女の心に刺さったらしい。その題名って……何だっけ? 『戦え!焼きいも』だったかな?
俺の作り話は、おむすびころりんとか三匹の子豚のような、ごくありふれた子ども騙しの童話だった。けれど、俺がお話を作ってあげると、ツクヨは面白いようにホイホイと釣れた。作るたびに入れ食いだった。俺の作るお話は、ツクヨホイホイだったのだ。
「サヨちゃんのおはなしは、おもしろい。ツクヨはつぎもまっています」
というように(笑)
夕食時にはピーマンで、朝食時には目玉焼きで。ツクヨと顔を合わすたびにお話を作らされた。ツクヨのお気に入りは“畑の天下一武道会シリーズ”である。何本作ったのか忘れたけれど、20本くらいまで作ったのを覚えている。ツクヨの成長と共に、俺の話もより凝った話に変化した。
俺の考案した武道会システムは、我ながら画期的だった。基本ルールは、対戦相手に勝利すると相手の味を奪えるというもの。その第一話。さつまいもの対戦相手はナスであった。じいちゃんのいもは強い。当然のように、さつまいもが勝利する。さつまいもは、ナスの味を奪い“さつナス”へと進化する。
「つぎ、つぎ。あたらしいの!」
ツクヨは、武道会の虜になった。
「じゃ、もうひとつ作ってやろうな」
小遣いで買ったマンガの山は伊達じゃない! 俺は可愛いおねだりに本気を出した。
次の対戦相手はきゅうりだった。その次はじゃがいも。そして、最後。よつぼしいちごに敗北する。じいちゃんのいちごはツクヨの好物だ。俺はさつまいも派だったけれど、可愛い姪っ子に花を持たせるのも叔父の役目だ。
「サヨちゃんのおはなし。もっと、もっと、かんがえて」
ツクヨの伝達力は光回線をも上回る。その伝達先はアヤ姉である。そして、俺にアヤ姉からの命令が下った。小学生の俺にとって、アヤ姉からの命令は絶対だった。
「サヨ! 悪いけど、アンタのお話、文字にしてプリントアウトしてくれない? すごーく、ツクヨが喜ぶのよねぇ。それから、文字は大きめにしといてね」
思いついたように、アヤ姉の口から命令が飛び出した。俺は今、すき焼きに集中していたいのだけど……。そんなのお構いなしである。あ、その肉は俺の……。ほら、オトンに取られた。オトンはいい感じの肉を選んでは、ツクヨの皿に入れてやる。
「プリンタない! 肉もない! 俺のやる気も全然ない!」
俺は、少しムッとしながら返事をする。いつの日か、アヤ姉にも食べ物の恨みが恐ろしいことを教えてやる。俺の返事に嘘はない。パソコンはあれど、肝心のプリンタがない。だから俺は悪くない。俺の言葉を完全に無視して、平然とアヤ姉は言葉を返す。その言葉は、オトンに向かって一直線に投げられた。
「プリンタなんてパパンに貰っちゃえばぁ? ツクヨちゃん、サヨちゃんのお話。楽しみだよねぇ(笑)」
「うん! ツクヨはたのしみ」
コロコロとしたツクヨの声に、オトンの箸が一瞬止まった……。オトンからすれば、ツクヨは可愛い孫娘。きっと頭の中でコンピュータが、ウィンウィンとフル回転しているのだろう。困ったような、うれしいような。オトンは、そんな表情でツクヨに肉を探している。
「サヨリにプリンタかぁ……」
きっと、カブトムシのトラウマがあるのだろう。プリンタに喜んで、何をしでかすのか分からぬ息子だ。しかも前科持ち。それでも俺は確信していた。オトンのプリンタ、ゲットだぜ(笑) そして、俺の予測はピタリ賞となる。
「そうか、そうか……だったら、じーじのプリンタをサヨリに譲るから。ツクヨの大好きなお話の本、叔父さんに作ってもらえ」
叔父さん、言うな!
予期せぬ棚ぼたで、俺はオトンからプリンタを手に入れた。すぐさま俺は、タマネギとナスとのバトル話を印刷した。俺は仕事がデキる男である。
「あら、もうできたん? 早いわね」
俺の仕事の早さを思い知ったか?姉貴殿。パソコンをもらった夏とは実力が違うのだよ。
日々のブログ投稿が、俺のタイピング速度を鍛え上げた。鈍足から爆速にまで鍛錬を重ねた。だから、俺のタイピング速度は桜木よりも速い! この程度なら、晩飯後だけれど朝飯前じゃ。
「じゃこれ、執筆料ね。お疲れちゃん」
アヤ姉はそう言って、俺に100円玉を手渡した。これが俺にとって、人生初の原稿料だった。オトンの次は、俺の脳内コンピュータが動き出す。1回100円、1ヶ月で3,000円。文字が金になるなんて……こいつは実に美味しい話だ。
欲が絡むと嫌でも執筆意欲が湧くものである。金に釣られると、アイディアが湯水のように溢れ出す。野菜の武道会場が、俺の脳内でより鮮明にイメージされた。頭の中に召喚した野菜たちは、勝手に戦いを始めた。こうなってしまうと、自分自身でも止められない。
俺は執筆料100円と引き換えに、ツクヨの専属ライターの地位を獲得した。何かを認められたような気がして、俺は有頂天になっていた。だから、ツクヨのお気に入りのお話をまとめた。そして、それを一冊の本にした。A4用紙に印刷してホッチキスで止めただけ。お粗末な本だった。けれど、自分で本が作れたことがうれしかった。
「ツクヨの本ができました」
俺の渾身の一冊だ。受け取ってくれ! 俺はニヤニヤしながら、ツクヨに本を差し出した。絶対、喜ぶぞぉ~これは。
「これ、ツクヨに? わーい!!!」
幼女らしい『わーい!!!』の声に、胸の中で熱いものが込み上げる。この感覚は……癖になる。
「サヨちゃんのほん。だいじにしないと。カバン、カバン……」
俺の本に喜んだツクヨは、ペコちゃんの絵柄のカバンに本を入れた。そして、俺の本を持ち歩き始めた。公園のお友だちをつかまえては、畑の天下一武道会を読み聞かせている。
その姿を見ているだけで、俺は小説家にでもなったような気分になれた。てか、4歳でひらがなを読めるって……どんなふうにアヤ姉は、ツクヨに文字を教えたのだろう。俺は小学生になるまで、自分の名前すら書けなかったのに……。
中学へ上がる直前の春休み。俺は、ツクヨを公園で遊ばせていた。それは、今日のアヤ姉からの命令である。春の空気がポカポカして気持ちいい。天に向かって背伸びをしていると、桜木が公園の前を通りかかった。
「何しょんな? 桜木」
「おや、飛川君。お久しぶりです」
桜木は、塾へ行く途中だと言う。俺と会話しながらも、桜木の視線が俺の太ももへと移動する。視線の先には、俺の足にじゃれつくツクヨの姿があったからだ。
「おやおや。可愛い彼女さんですね」
すっと膝を落として、桜木はツクヨの顔の高さに目線を合わせた。この気遣いが俺にもあったら、今頃は誰かとデートでもしているのだろうな……。
「こんにちは。飛川君に、こんな小さな妹さんがいたとは。今まで全然知りませんでしたよ」
安定の桜木スマイルは健在だ。
「この子は俺の姪っ子ちゃん」
俺は、ツクヨの頭を撫でながら桜木に答えた。
「そうでしたか。どおりで僕が知らないはずです」
「それよりも春休み。桜木は、どっかに行った? 今、話しする時間ある?」
俺は少しだけでも、桜木と会話がしたくなった。ブログのコメントからの会話はあるけど、ネットとリアルとでは別物だ。
「少しならありますよ」
やった。
俺たちは、桜の木の下の青いベンチに腰を掛けた。そして、コメントには書けない近況報告を話し始めた。ツクヨは俺の隣に座って、俺が書いた本を読み始める。それに、桜木レーダーが反応した。
「ところで、飛川君。それは何ですか?」
桜木は、ツクヨが持つ本を指さした。眼鏡を一度上げてから、ツクヨの本に注目している。桜木は興味を示すと、眼鏡を上げる癖がある。その癖が俺の本へ。それが少し恥ずかしかった。やだよぉ……気になるのかい? 聞きたいか? 聞かせてやろうか? 桜木さんよー!
「あ、これ? ツクヨに作ってやった本。畑の天下一武道会シリーズってんだ」
俺は込み上げる笑みを必死で堪えた。
「ご自身でお作りになられたのですか?」
そう、そう、そう。もっと、聞いて。何なら、褒めて。
「ま……まぁ~な(笑)」
本……そのワードに、桜木が反応しないワケがない。彼の読書にジャンルはないのだ。桜木は、文字なら何でも読む男だった。たとえそれがレシピであっても。
たとえば、去年の林間学校。そこで、カレーを作った時の話。カレーのルーより、桜木は空き箱に興味を示した。みんなが家から持ち寄ったカレーである。メーカーだって多種多様だ。桜木は、その空箱を集めまわり、箱の裏のレシピを読み始めたのだ。
「あのさ、桜木。そんなの一個でいいじゃねぇ~の?」
「だめです」
桜木は、俺の言葉に耳を貸さない。カレーの作り方なんてどれも同じだ。誰だってそう思う。桜木は、ひとつの空き箱を俺に見せた。表ではなく裏側だった。
「各メーカーの特色があって面白いですよ。ほら、飛川君。このメーカーの説明は、他社のと違って個性があります。そして、香辛料にもこのメーカーだけの……。ゆきさんの箱を見てください。このカレーは外国製ですよ」
桜木は、楽しげである。
カレーの箱の裏には、聞き覚えのない単語ばかりだ。桜木の話が、俺には理科の授業にしか聞こえない。てか、ゆきのカレーの説明書き。これって、どこか外国の文字で書いてあるぞ……たぶん。桜木は、異国の文字すら読む男。そんな高性能レーダーに、俺の本が反応したのだ。もう、こんなの、うれしいじゃん(笑)
「えっ? これ、飛川君が書いた本? ねぇ、ツクヨちゃん。少しだけ、その本、僕に見せてくれるかな?」
ツクヨに桜木が問いかける。
「いーよーぉ!」
よし、いい子だ。今日も元気なツクヨであった。桜木がページをめくるたびに、
「このね、おはなしはね……」
ツクヨはあらすじの説明をし始める。桜木はツクヨの解説を聞きながら、うんうんと頷いている。その眼差しが、ページをめくるごとに真剣味を帯び始め、目に見えない緊張感すら感じ始めた。
俺って、また何かをやらかした? 桜木の変化に、カブトムシのトラウマが俺の心を不安にさせた。その様子に何かを察したツクヨは、しれっとブランコで遊び始めた。
「飛川君、これ、お幾らですか? ぜひとも僕に譲ってほしいのですが!!!」
読了した桜木からの第一声がこれである。状況がつかめない俺は、咄嗟に反応ができなかった。
「は?」
何、言ってんの?
「僕は、この本が気に入りました。如何ほどでお譲りくださいますか?」
俺の本を……買う?
桜木の言っている意味が分からない。桜木は、至極真面目な顔である。真っ直ぐな目で言われても、親友から金なんてもらえない。そんなの、俺のスタイルじゃない。
桜木には、ブログを作ってもらった恩もある。その後で、プリンタまでもが手に入ったのだ。
「ツクヨ。あのお兄ちゃんに、この本をあげてもいいかな?」
「やだ!」
「ツクヨには、俺が新しい本を作るから。新作やで、そこのお嬢ちゃん」
「しんさく……」
ツクヨは、新作の言葉に快諾した。
「だったら、あげるよ。ブログの恩もあるし」
俺は、桜木に本を渡した。
「ありがとうございます。大切にしますね」
この言葉を残して桜木は塾に向かった。あの読書家が、俺の本に興味を示し、譲ってほしいと俺に言った。なんか……凄くね? 俺は、凄い奴に認められた気がした。
それに自信を得た俺は、気に入った与太話を厳選し、ブログに投稿し始めた。大きな反響はなかったけれど、どこかの誰かに読まれている。そんな見えない手応えをビシビシと感じていた。
そんな俺が、中学生になる日。それを、指折り数えて待っている女がいた───アヤ姉である。
「あんたもう、中学生になるのよねぇ。中学生は大人だもんねぇ。もっと、お家のお手伝いもしないとねぇ(笑)」
俺が中学に上がった途端、アヤ姉からの命令が増えた。その全てがツクヨ絡みの案件だった。アヤ姉からの新たなミッション。それが幼稚園のお迎えである。そこは、かつて俺も通った幼稚園。懐かしの学び舎に、姪っ子ツクヨを迎えに行く。それは、誰にでもできる簡単なお仕事であった。
ツクヨが俺を待つ幼稚園。懐かしの門をぬけると、俺は女性アレルギーになっていた。

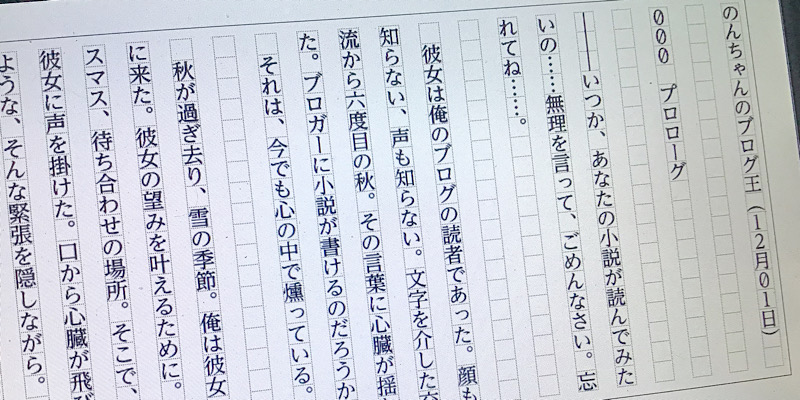





コメント