014 オッツーの変身ベルト
───はじめまして、ゆいです。ぶしつけですが、折り入ってカブトムシさんにご相談があります……。
旅乃琴里、桜木、のん、そして───ゆい。
揃いも揃って、俺に小説を書けと言う。正直、俺は困っている。書くべきか、書かざるべきか。そもそも、俺に小説が書けるのか? いや、書けないに決まってる。
今の俺の実力。それを総動員しても、書ける気が全くしない。クリスマスまでの時間もない。ツクヨに作ったお話とはワケが違う。文字数の壁もある。小説に必要な文字数は、俺の書く記事の50倍だ。下手すりゃ100倍。絶望的な文字数に腰が引けた。どう考えても無理ゲーだ。
プロットすら思いつかない。
もう、俺の頭じゃ処理ができない。だから、桜木に助けを求めた。
───少し、時間を取れないか?
桜木にメッセージを飛ばすも、桜木からの返事はなかった。きっと、塾が忙しいのだろう。こう見えても、俺たちは受験生だ。こんなことで、無理も言えない。明日、学校で相談しよう。
「はぁ……今日は一段と寒いなぁ……」
吐く息が白い……。
ってか、まだ9月だぞ? 地球温暖化はどこ行った? こんなの、真夏から真冬じゃないか? 陰謀論じゃないけれど、地球の終わりを感じてしまう。『今は氷河期です』とか、御用学者に煽られそうだ。今の俺には、そんなのどうでもいいけどな。
そう、今はそれじゃない……。
俺は、夕暮れの公園のベンチで黄昏れていた。貧乏な高校生は、公園で黄昏れるものである。あー、ケツが冷たい。俺は自動販売機で缶コーヒーを買った。それで両手を温めながら、沈む夕陽を眺めていた。
───シャーッ!
背中越しに、自転車の音がする。それは、聞き慣れた音であった。ゆっくりと俺は立ち上がり、クルリと背中を夕陽に向けた。
───夕陽に向かう仮面ライダー。
思ったとおりだ。音の主はオッツーだった。プライベートは、いつも腰に変身ベルトを巻いている。昭和、平成、令和と仮面ライダーは世代交代を繰り返すけれど、オッツーのベルトは1号ライダーだけである。本郷猛の生き様に、美意識を感じているのだと彼は言う。
「いつ見ても、ベルト姿が絵になるなぁ」
誰が見ても不自然なはずなのに、腰の変身ベルトに違和感すら感じない。そこが、オッツーの凄いところだ。むしろ、腰にベルトがないオッツーの方が、どことなく不自然に見える。変身ベルトも『継続は力なり』だな(笑)
「シケた顔して何やってんの? サヨっち」
オッツーは、腰の変身ベルトのスイッチを入れた。俺の空気を察した奴なりの景気づけのつもりだろう。ギュイーーーーーン!!!とベルトの風車がうなりを上げた。
「いつ見てもカッケー風車だな」
「タイフーンな(笑)」
すかさず、オッツーはツッコミを入れた。
見慣れたはずのタイフーン。それに元気が出るのは、男の本能がそうさせるのだろう。本能とはそういうやつだ。いつもそう、いつだってそう。腰のタイフーンの輝きを見るとワクワクする。
タイフーンに見とれている俺に、オッツーが語りかけた。
「あ、聞いたよ、小説の話。スゲーな、お前が小説だって」
何で知ってる?
「情報源は桜木か? ブログ書きの俺にゃぁ、全く無理な案件だけどな。桜木の奴……わざと返事しなかったな。で、お前を仕向けたわけか?」
「ま、そんなところ。お前さ、書けると思うよ。ブログみたいに書けばいいじゃん。面白いぜ、お前のブログ。それを毎日書き続けるって、それもひとつの才能ってやつなんじゃね? 知らんけど」
いつもと違って、オッツーの顔は神妙だった。いつもと違う猛の顔だ。太い眉毛がハの字であった。
「簡単に言うなって。俺だって、密かに何度かチャレンジしてんだよ。でも、あれは沼だ、泥沼だ。迂闊に足を突っ込んだら、俺のバカがばれるだろ?」
「そんなもんかねぇ?」
オッツーは首をひねる。
「そんなもんだよ。まぁ、でも、あんがとな(笑)」
オッツーは照れくさそうに頭を掻いた。すると、オッツーのスマホが鳴った。画面を見るなり慌て始めた。緊急の連絡のようだ。
「悪ぃ、オレ、すぐにでも帰らないと!」
「どうした? 事件か?」
「そうなんだ。オレんち今夜シチューなんだ」
「そっか……それは仕方ないな(汗)」
ふたたび自転車で走り出すオッツーを、俺はぼんやりと見送った───そっか、シチューなら仕方ない。なぁ、オッツー。あれから何年が経つのだろう……。
オッツーのロードレーサーが、青信号の前でピタリと止まった。青信号なのにピタリであった───どうしたよ、パンクでもしたか?
オッツーご自慢のロードレーサー。それが、180度方向転換すると、猛スピードで戻ってきた。どうしたよ“帰ってきた”は、ライダーじゃなくてウルトラマンだろ?
「オレ、いいこと思いついたんだ! もの凄くよきことをだ(笑)」
「よきこと?」
何だよその目は。ツゥインクルしてんじゃん! あの目は、オッツーの悪巧み。昔っから、そうである。腰にライダーベルトを巻いて、実に悪い目をしている。正義の味方は、どこへ行った?
「小説、書いちゃいな(笑) それを、みんなで読んで評価するから。全員が“〇”を出したら、お前だって自信もつくだろ?」
オッツーは、続けて悪巧みの根拠を語る。
「こっちには、スーパー読書家の桜木と、同人作家のアケミと、教養博士のゆきちゃんがいるんだぞ。控えめに言っても、全員を唸らすのは難関だろ? 全員の太鼓判なら自信だって持てるだろ? ねぇ、オレって凄くね?」
ちょっと、お前……凄いかも?
オッツーは、ふたたび腰のベルトを回転させた。とっぷりと日が暮れた暗がりで回るベルト。その輝きが眩しかった。
お前さ、そんなに回してたら電池切れるぞ(笑)
「で、話の中にオッツーの名前がないんだけど?」
それは、至極当たり前の疑問である。
「だって、お前の全部、文字ばっかだからな。それに小説は長いから。ブログとは違うんだよ(汗) オレに頭脳労働は似合わないし、お前のじっちゃんの力仕事の時に呼んでくれ。いつでも、正義の味方が力を貸すぜ!」
自信なんてあるもないも、書いてみないと分からんか……。でも、なんだか元気出た。オッツーはやっぱりヒーローだ。お前に言われると、書けない小説が書けそうな気にもなる。
でも、まぁ。なんか……ありがとな。
「ありがと……」
俺から、お礼の言葉が出る幕はなかった。オッツーの姿は、瞬く間に闇に消えた。そうだった。今夜はシチューか……。赤い夕陽も海に沈んだ。身も凍る冷え込み具合に、俺も撤収することにした。風邪を引いては元も子もない。
家に帰ると、俺に向かってツクヨが叫んだ。
「サヨちゃーん! 今夜はシチューだお(笑)」
奇跡のシンクロニシティの夜であった。いや違う。オカンもきっと覚えていたのだ。オッツー家のシチューの意味を。
その翌日。
放課後クラブの緊急会議が開催された。会場は俺の部屋である。こいつら、ガキのころから我が家の常連だから、どいつもこいつも顔パスだ。高校に入って、急に背が伸びたオッツーだけが、オカンに職質を受けたくらいだ。放課後クラブのメンバーたちが、我が家のように俺の部屋でくつろいでいる。
でも、これって、くつろぎすぎじゃね?

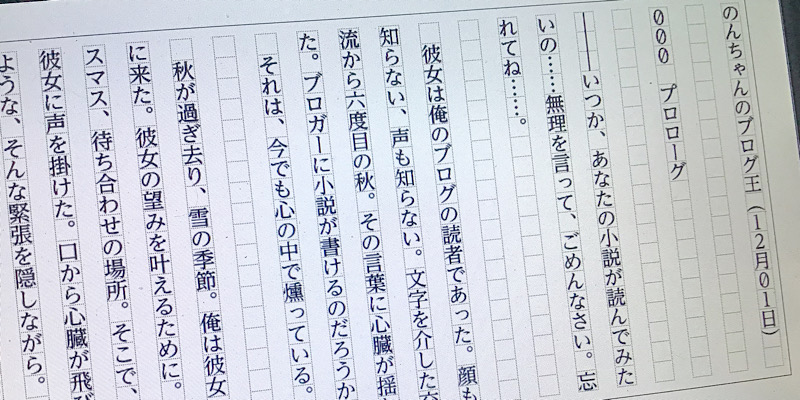





コメント