017 男の気持ち、女の気持ち
小説を書く。
そうは言っても、俺には致命的な欠陥がある。小説クラスの長文が書けないのだ。これでも6年間、毎日ブログを書き続けた自負もある。だから、文字数伸ばしくらいなら手慣れたものだ。無理をすれば、俺にも長文くらい書けるだろう……でも、書けない。
書けないというよりも、文字数を伸ばすと間延びするのだ。言葉のリズムが間延びして、ノイズが入ってテンポが崩れる。そうやって書いた文章を、後で読み返すと気持ちが悪い。自分で書いた文章なのに嫌になる。
ならば、登場人物を増やそうか? その回避策も考えた。物語に新たな要素が加われば、文字数は勝手に伸びる。でも、それにも問題があった。誰かが動けば何かが起きる。登場人物の数だけ、ストーリーに複雑さが加味される。
そのうえ、性別、身長、体重、性格、容姿……新たなキャラ設定も考えないと……。すると、どうなると思う? バカな俺の脳がついていけない。物語が進むにつれて、キャラ同士の整合性が怪しくなる。それも困る。
かといって、ストーリーの風呂敷を広げすぎると無理が生じる。ツクヨの人類滅亡。そこまで風呂敷を広げれば、皆殺しのバッドエンドか、地球脱出の道しか思いつかない。
どうにかして地球脱出に成功しても、ふたりが他の惑星で幸せをつかめるだろうか? その答えはノーである。俺の無知さが、地球脱出を阻止するからだ。
物理法則とか、天文学とか、生物学だとか。そんな高度な設定が俺にはできない。つまり、魔法のような奇跡でも起こさなければ、俺の考えた物語の全てがバッドエンドになってしまう。不思議の国の夢オチは禁じ手だ。
のんは、どんな物語を好むのだろうか? 少なくとも、クリスマスプレゼントに人類滅亡のシナリオだけは望まないだろうな。
───男は妄想、女は現実。
ふと、アケミの言葉が俺の脳裏を過った。それは“ぼっくり会”で、アケミが先輩男子たちに放った言葉だ。
ぼっくり会の正式名称は“ひとりぼっちのクリスマスの民が集う会”である。簡単に言ってしまえば、学校非公認の合コンだ。参加資格は、在学生でリア充以外。桜木を除いた放課後クラブの面々は、面白半分で1年生から参加しているイベントだった。
去年、その会場で事件が起こった。
くじ引きで、ゆきが座った席が悪かったのだ。ゆきは先輩男子に囲まれてしまった。次のくじ引きまで、ゆきはどこにも逃げられない。
───新しいガンダムがアニメになるって知ってる?
ゆきを囲んでガンダム談義が始まった。ゆきはガンダムを知らない。でも、先輩たちの手前もある。借りてきた猫のように、愛想笑いで頷くだけだ。
それから小一時間ほどが過ぎたころ、アケミがゆきの異変に気づく。間髪入れずに、アケミはガンダム談義に割って入った。その光景は、俺の目から見ても怒鳴り込みだ。
「あんたらねぇ、バッカじゃない? 男は妄想、女は現実よ!」
先輩たちはあんぐりだ。少し離れて見ていた俺たちもあんぐりだった。張本人のゆき以外はアケミの怒りを理解できない。俺たちは取りつく島もなく、アケミは続けざまに怒鳴り散らした。
「ガンダム、ガンダムって、男どもはやかましいのよ。女の子はね、ガンダムなんて興味がないの。『アムロ、行きまーす』って、行かないの」
行かないのか……。
「わがままな天パは好みじゃないの。ザクの話もお呼びじゃないの。ドムも、グフも、ズゴックも知らないの」
お前、かなりガンダム知ってるよな?
「もしも、あたしらが魔女っ子とか、日々蝶々とか、NANAとか。そんなの本気で語り始めたら、先輩たちは、何時間も笑って頷いてられる? この子にはね、ガンダム談義が苦痛なのよ!」
勉強になりました。アケミ様、ごもっともなご意見でございます(汗)
アケミがゆきに向かって指をさすと、その場の空気が凍てついた。先輩たちからの反論を恐れて、ゆきは小さく固まっている。アケミは全く動じない。すぐさま運営に向かって声を荒げた。
「運営! くじ引きやって!」
アケミの希望で、新たな席替えのくじが参加者全員に配られた。
───あの子、誰? ステキだわぁ。
アケミの発言が女子生徒の共感を呼び、男子生徒は口を閉ざした。アケミの武勇伝は伝説となり、後世に語り継がれていくことになる。
一説によると、一部の女子の間で、アケミファンクラブが結成されたらしい。
───だよなぁ、男と女じゃ違うもんなぁ。
俺が書くのは、女の子が読む小説である。書くべきは、もっと身近なドラマであろう。男目線のストーリーなんて、最後まで読んでもらえない。頑張って書いても、がっかりされては本末転倒。男は妄想、女は現実よ! か……。
男に女の気持ちは分からない。たぶん、アルキメデスの時代からそうなのだ。その謎を解明するには、いくつ命があっても足りやしない。とりあえず、書くのみだ!
日常に非日常を織り交ぜて、ガリガリと書いた原稿を読み返す───ダラダラだった。俺は思いきって、余計なエピソードと文字をカットした。それでも3万文字を超える文字数になった。俺にしては超大作で、俺にすれば上出来だ。
その原稿をオトンのプリンタで印刷し、桜木、アケミ、ゆき。放課後クラブの面々に手渡した。
「では、放課後に」
桜木の回答に、俺は思った。知ってる、それ嘘でしょ? 桜木が授業中に、俺の大作を読破するというのだ。
「飛川君、がんばりましたね。処女作が、これだけの文字数になるとは思いませんでした。書けて1万文字かと思ってましたよ。では、放課後に結果をお伝えしますね。そうですね……我々が、あなたのクラスに参上します(笑)」
朝出して夕方バッチリ? お前ら、クリーニング屋さんですか?
「桜木、それは無理だろ? お前は読めそうだけれど、そんなに早くアケミとゆきが読めるのか? 俺には到底信じられんのだが」
眉一つ動かさず、桜木は淡々と答える。
「これくらいなら大丈夫でしょう。これは審査ですからね。味わうわけでも、読み込むわけでもありません。審査用の読書術というのもあるんですよ。飛川君はご心配なさらないで(笑)」
知らなかった。審査用の読書術……。そんな便利な機能が俺にはない。
「既に同人書籍を販売しているアケミさんは、ある意味でプロの領域ですし、ゆきさんの恋愛小説キャリアもバカにはできません。そして、かぐやさんは女性ですから、彼女たちの感想こそが重要です(笑)」
スカッと爽やかな笑顔で簡単に言う。本当にそれができるのか? 俺は半信半疑で教室に戻った。すると、オッツーが、手ぐすね引いて待っていた。
「もう書けたんか? お前、速いな……アクセルべた踏みで書いたのか? で、オレの分は? 早くオレにも読ませろよ」
読まないって、俺に宣言して帰ったくせに……忘れたのか?
「楽しみにしてもらって悪いけど、お前のは……ない」
「どうしてだよ、オレたち親友だろ? 悲しいことを言わないでおくれよ」
オッツーよ、その気持ちだけ受け取っておくよ。でも、どうせ読まないんだろ? 期限は今日の放課後なんだぜ……。
「もちろん、お前は俺の親友だ。この前、長文はって言ってたから遠慮したんだ。放課後までに読んでくれるか? 仲間はずれにしてすまなかったな。これだけど……」
俺は自分用の原稿を、オッツーの机の上に乗せて見せた。A4コピー用紙がドサッって感じだ。オッツーの顔色が青ざめた。
予想どおりの反応だった。
「オレ、こんなにたくさん、ワイルドスピードで読めないわ……なんか、ごめん」
ありがとう。分かってくれたか、親友よ。
俺とオッツーは、いつもどおりに授業を受け、いつもどおりの弁当を食い、いつもどおりの放課後を迎えた。授業終了のチャイムが鳴り、ホームルームと掃除が終わる。
部活、塾、帰宅、放課後デート?……クラスメイトたちは、次の場所へと散って行く。静まり返った教室の中、俺とオッツーだけが残っていた。審判の刻を待つために。
「君たち、何時までいるつもりなのかね?」
施錠にやってきた担任が俺たちに声を掛けた。マズい……そんな空気が流れた。
「桜木君に、ここで待つように言われちゃって」
照れくさそうに頭を掻きながら、オッツーが先生にそう答える。グッジョブだ(笑)
「隣のクラスの桜木か? だったら、飛川に教室の鍵を預けるから、お前が施錠して、鍵を職員室まで持ってくるように。職員室に私がいるから。あ、桜木によろしくと伝えておいてくれ」
桜木君、君は何者?
俺たちの高校で、“秀才桜木”の名は、水戸黄門の印籠に匹敵する。たとえば、この教室で“ジャンボリ キャンプだホイ!”をやると言っても、桜木さえ参加すれば、無謀なリクリエーションだって容易く許可されるはずである。
これが高校3年間で、桜木が築き上げた信用というやつだ。いやはや、きっと将来は日本を背負う男になるのだろう。
「お待たせしました」
担任と入れ違いに、桜木、アケミ、ゆきが教室の中に入ってきた。どういうワケだか、ゆきが緊張しているように見えた。違和感というより嫌な予感とはこれである。
審査発表のひとり目は桜木だった。
「人類滅亡は諦めたようですね。僕もそれは厳しいと思っていました。かぐやちゃんへのプレゼントですからね。誰一人として死なない物語が理想です。でも、こっち側の作風になるとは……僕の予想を超えてきましたね。いや、とても楽しめましたよ。“〇”です(笑)」
やった! ひとつ目の難関を乗り越えた。心から俺は安堵した。俺の予測では、厳しいのは桜木とアケミである。次のアケミさえクリアすれば、ゆきは義理で“〇”をくれるに違いない。思ったよりもチョロいぞ、これは。
ふたり目はアケミである。
「初めてにしては悪くないと思うよ。お話になってるし、最後まで引き込むような何かもあったわ。それが、私にもよく分からないけどね。でもね……」
「でもね?」
俺とオッツーの声がハモる。
ヤバい空気がビシビシ伝わる。やめてくれ! “でもね”の後は否定だろ? そんなの“×”マークの予告じゃないか。
「ごめんね。これじゃ売れない。だから“×”」
終わった……俺の人生、終わっちまった。そして、最後のトドメがゆきである。
「えっと、わたしも読ませる何かを感じたよ。でもね……」
また“でもね”……か。
「ちょっと違うの。ごめんね“×”なの」
初審査は散々だった。
桜木以外、すべて“×”。この後で、俺に罵声を浴びせたのはアケミだった。同人誌の執筆と製本。それに、命を懸けているような女である。それを闇で売りさばく作家でもあった。
今なら、データだけをネットで売れる時代なのに、頑なに紙媒体にこだわる女だ。それだけに、俺の小説に対する指摘は厳しい。
「サヨちゃん! あんたさぁ、表記ゆれゆれなのよ!」
「何を言ってるのか、さっぱり分からん……」
教室から桜木とゆきが去った後、俺はアケミにブチのめされた。あいつの言葉は拷問だった。アケミは真のドSだ。心の傷口の中で、矢継ぎ早にトゲトゲしい語彙が弾けた。さすがは言葉のプロである。心が……痛い。
「じゃ、次は売れるのを持ってきて!」
……売り物じゃないのに。
心がボロボロになった俺は、息も絶え絶えに椅子からゆっくりと立ち上がった。すると素早くオッツーが俺の肩に手を乗せた。やっぱり、俺にはオッツーだけだ。
「オッツーよ、お願いしてもいいか?」
いつものように、お前の風車を回してくれ。俺のリクエストに応えるように、オッツーは大きく頷き変身ベルトのスイッチを入れた。
───ギュィィーーーーン!
ベルトの効果音の余韻に浸っている俺に、オッツーが口を開いた。
「お前、アケミとSMプレイ中だったじゃん。だから言いそびれたけど、桜木からの伝言な。しっかり手直しをしたら、今日みたいに来週原稿を提出してほしいだってさ」
「お、おう……」
そう言って、俺は膝から崩れ落ちた……。

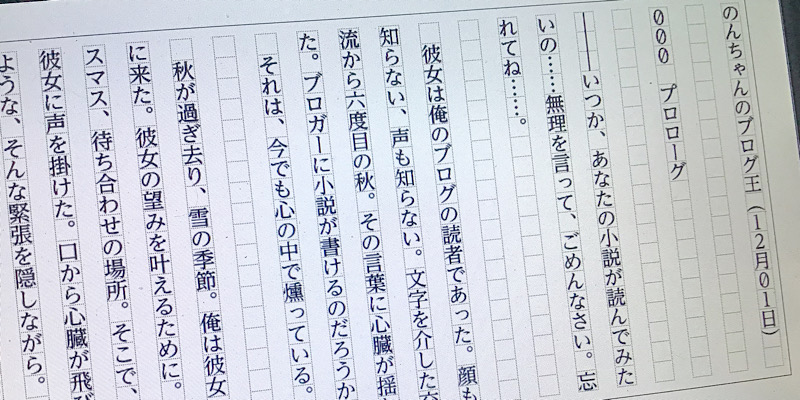





コメント