019 最高の裏切り
この1週間、俺は休む間もなく小説と格闘していた。人間の脳は、限界を超えると安全装置とやらが働くらしい。水曜日、俺は人生で初めてそれを体験した。何も考えられなくなったのだ。
───どうなった? 俺の頭……。
予期せぬ脳からの急ブレーキに混乱した。こんなの初めて。全く頭が働いている気がしない。もう、何も考えられない。俺はその感覚に恐怖した。
「俺の頭がこんなんじゃ、今日の更新が不能になるかもしれないぞ……」
その恐怖の矛先は、小説ではなくブログに向かった。俺が最も恐れているのは、ブログの更新が止まることである。
ブログだけは絶対に止められない。のんは心配性なのだ。更新が止まれば心配するに決まってる。俺は今日の小説を諦めて、すぐさまメールチェックを開始した。のんが俺の異変に気づけば……。やっぱりだ、俺の勘は的中した。
メールボックスに、のんのメールを見つけた。
───こんばんは。のんです。最近、疲れてないですか? なんだかそんな気がして心配です。わたしでは、何のお役にも立てないかもしれません。でもね、何かあったら何でも相談してください。生意気なことを言って、ごめんなさい。
生意気じゃないぞ、可愛いぞ(笑)
のんの言葉は魔法のようだ。のんのメールで俺の脳は覚醒した。今なら幾らでも書ける気がする。
───大丈夫ですよ、心配ないっす。
俺はのんへの返信を書き、ブログを書き、小説に戻った。
そうやって仕上げた三度目の正直である。3万字だった文字数も、その倍にまで膨らんだ。我ながらの自信作。もうこれって、このまま出版社にだって持ち込めそう、そんな気にもなる出来映えだった。
これで次のステップに進める。ようやく先へ進めるのだ。意気揚々と審査を受け、俺は地獄に落とされた。
「残念ですが、今回は“×”ですね」
予期せぬ人物からの、まさかの“×”が……。
それは、アケミではなく桜木だった。この日、アケミの評価は“〇”だった。“×”の評価を下したのは、安全パイだと信じていた桜木であった。
───何でだよ!
目の前が真っ暗になったと同時に、俺の頭に血が上った。
「何でだよ! これまでのアレは何だったんだ!!!」
思わず俺は桜木の胸ぐらをつかんだ。
「サヨっち、落ち着け! カッカすんなって!」
俺の両脇にオッツーの長い腕が巻きつき、そのまま体ごと後方へ引きずられ、ゆきはその場に泣き崩れてしまった。
「お前は、正義の味方じゃなかったのかよ!」
オッツーの腕の力が緩むことはない。
「それはそれ、これはこれ」
どんなに俺が抵抗しても、オッツーの巨漢はピクリともしない。オッツーに羽交い締めにされた俺を、桜木は冷ややかな目で見つめている。
「あなたの努力に一定の評価はします。誰に見せても恥ずかしくない作品だとも思います。この短期間で、しかも初めての作品で、この領域まで登りつめた。あなたの努力と才能は、驚嘆にも値するでしょう。素晴らしいの一言です」
桜木からの言葉は氷のように冷たかった……淡々と静かな声だ。
素晴らしいなら“〇”をくれよ! 努力の全てが振り出しに戻ったのだ。怒りが収まらない俺と桜木との間にアケミが割り込んだ。
「だったら何でよ?」
アケミの声が怒りに震えていた。あのアケミがである。
「この作品は基本どおりよ。キチンとルールどおりに書いてある。そして内容も面白いわ。サヨちゃんは初めて書いたのに、こんなの生み出してしまったのよ。これでダメなら全部ダメよ。桜木君、サヨちゃんに何か恨みでもあるの? ねぇ、あんた。反論あるなら言ってみなさいよ!」
アケミの言葉にも、桜木は淡々と答えた。その目は冷淡そのものだった。この瞬間のために桜木は俺の審査を続けたのか? そう、思えるほど冷たい目だった。俺の親友の視線は死神の目であった。俺にはそんなふうに見えたんだ。
「アケミさん、あなたもアマチュアとはいえ、作家ならご理解できませんか? この作品には、スッポリと抜け落ちた部分があることを。僕は、これをかぐやちゃんに渡すくらいなら、いっそ1作目をお渡しした方が喜ぶだろうと考えています。アケミさんだって、それに気づいているのでしょ? 飛川君には、今が大事なんですよ! あなたは黙ってくれませんか?」
桜木の鋭い視線に、アケミはハッとした顔をして口を閉ざしてしまった───あのアケミをひと睨みで……。
「飛川君。もう、時間がありません。次で最後にしましょう。僕からのアドバイスは、たったひとつです。飛川君が僕にくれた“畑の天下一武道会シリーズ”を覚えていますよね?」
続けて桜木が俺に語る。さらに冷たいドライアイスのような低い声で。
「桜木が、俺に売ってくれって頼んだやつか?」
それは、小学生最後の春休みに、俺がツクヨに書いた本である。
「そうです。あの本です。僕は今でも持っています。そして、今でも読み続けています。何故だか分かりますか? 飛川君」
「……」
俺は、答えが分からなかった。
「あの作品には、その魅力があるからです。自分で自分の才能を潰さないでください! それを一番悲しむのは、彼女自身であることを自覚してください!」
桜木の気迫に力が抜けた。俺は黙ってうつむいた。
「ゆきちゃん……大丈夫? もう、帰ろう」
アケミは、床にしゃがんで泣いてるゆきを抱き起こした。
「大丈夫だよ、アケミちゃん……」
ゆきの背中を摩りながら、アケミはゆっくりと教室を出た。その後、すぐに桜木も教室を後にした。
「オッツー、ありがとな。もういいよ……」
俺はオッツーの腕をタップした。
「大丈夫か? サヨっち……」
オッツーが腕をほどくと、俺はその場に座り込んだ。呆然とぼんやりと、ボツになった原稿を眺めた。もう、最悪の気分だ。最後の最後に桜木が、俺から梯子を外すだなんて。俺には、それが信じられなかった。
「よっ!」
ポンっと、オッツーが俺の肩を叩いた。オッツーは、カチッとベルトのスイッチを入れると、タイフーンが勢いよく回った。
───ギュィィーーーーン!
「サヨっち! 困ったときは、じいちゃんだ!」
オッツーは、そう言い残して教室を出た。職員室へ教室の鍵を返しに向かう途中。2階の階段の踊り場から、誰かの話し声が聞こえた。でも、今の俺にはどうでもよかった。体が泥のように重くて吐き気がする。
高校からの帰り道。
誘い込まれるように、俺はじいちゃんの畑に寄った。どの道を歩いてきたのか? その記憶がまるでない。畑を見渡すと、じいちゃんが秋野菜を収穫していた。
今の時期なら秋ナスか……。

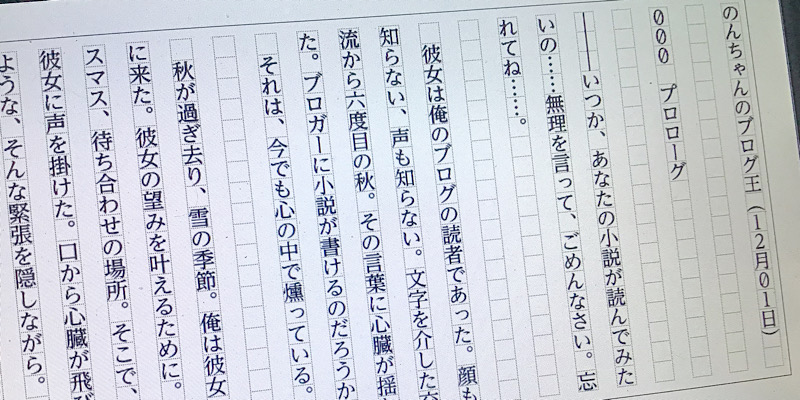





コメント