020 じいちゃん
3度目の審査の帰り道。
俺はじいちゃんの畑に寄った。オッツーからの助言もあって、じいちゃんと話がしたくなったのだ。俺には、じいちゃんに悩みを打ち明けた過去があった。
───ブログをやめたい……。
そう、愚痴った日。
俺は中学卒業を間近に控えていた。俺の愚痴に、いつもトボケたじいちゃんが真顔になった。
「三縁も春には高校生か……」
そう言って、じいちゃんは黙り込んでしまった。しばらくの沈黙の後、決意したように口を開いた。
「この話は、ワシとお前だけの秘密じゃぞ。約束できるか?」
「……」
俺は無言で頷いた。
小春日和の畑のベンチにふたり並んで腰掛けると、じいちゃんは遠い想い出を語り始めた。
今でも、俺は覚えている。じいちゃんの淡い恋物語。それが、今の俺と似ている気がした。ふたりは手紙だけの関係だった。文字だけで心を通わせていた。俺たちと同じだった。
「昔はな、ビンの中に手紙を入れて、海に流す遊びがあった……」
じいちゃんの時代には、インターネットなんてなかったそうだ。通信の主流は電話か手紙。そんな時代に、空きビンに手紙を詰めて、海や川に流す遊びがあったと言う。風船に付けて飛ばす人もいたのだとか。
それは、見知らぬ相手と文通をするためである。それが縁で、結婚したカップルもいたというのだから驚きだ。
「空きビンを海や川に流したの?」
それはステキな話だけれど、俺の疑問は当然だった。今なら、各種保護団体が目くじら立てる案件だ。自然を汚してはいけない。
「じいちゃん、それって怒られるやつやん?」
「そうじゃのう。でも、それが流行じゃった……」
じいちゃんは、苦笑いをしながら俺の疑問に答えた。
俺たちの時代からすれば、じいちゃんの時代がおおらかに見えた。そんな遊びが、今の若者の間で流行でもしたら、自然破壊とか生態系問題とかで、マスコミが喜んで飛びつくだろう。
物事の考え方が今とは何か違った時代。
じいちゃんが中学のころ。友だちと海へ行くのが日課だったそうだ。その目的は分からない。きっと、釣りでもしたのだろう。
ある日、波打ちぎわに漂うビンを拾ったそうだ。ビンの中には手紙があった。じいちゃんは、その住所に手紙を出した。それは、思春期の好奇心だった。でも、手紙の返事はなかった。
───手紙はいたずら。
じいちゃんが諦めそうになった時、さくらと名乗る少女から手紙が届いた。ビンの流し主からの手紙だった。
「ワシらの時代でも、ビン流しはテレビの話かと思っていたんじゃ。まさか、本当に返事が来るとはな……」
照れ隠しなのだろうか? じいちゃんの顔がしわくちゃになった。
その交流は、月1、2回のペースで2年ほど続いた。当時、若者の間では、文通相手をペンパルと呼んだらしい。文通が始まってから3度目の冬。彼女からの手紙がプツリと切れた。
「で、どうなったの?」
俺は、話の続きが気になった。
「返事は届いた……」
手紙の返事は、その翌年、さくらの季節に届いたそうだ。手紙の送り主は彼女の母親だった。手紙には、彼女の訃報が書かれていた。
俺がブログをやめたいと言った日。想い出を語り終えたじいちゃんは、淡々と悲しげに、遠くの空を眺めていた。
そして……
「お前がやめたければ、ブログなんてやめればいい。お前の好きにすればいい。でも、ワシは知っとるぞ。カブトムシのころから、お前に声を掛け続けている子……のんって子をな。コメントに誰も書き込まなくなっても、あの子だけは書き続けてるやろ?」
「のんは、猫のころやって……」
じいちゃんは勘違いをしている。のんからの初コメントは、猫の記事を書いた時だ。
「忘れたのか? あの子はカブトムシのころから、お前のブログを読んでいた。お前の知らないずっと前から、あの子は“見えない声”を掛けていたはずじゃ」
俺は何も言えなくなった。
「ワシは、あの子がさくらさんに思えてな。お前が書くのをやめたら、あの子はきっと悲しむじゃろうな。ひとりでも、お前のブログを読んでくれる人がいるんじゃから、大切にしてやらんとな……」
これが俺のじいちゃんだ。
あの時、じいちゃんと話さなければ、俺はブログを閉じていたかもしれない。そんなじいちゃんが、今も俺に声を掛けてくれる。心がボロボロになった……俺に。
「何ができよんな、三縁? 何かあったか? 今日は、ツクヨと一緒じゃないのか?」
「今日はひとりだよ、俺は学校帰りだから。ツクヨは家だろ?」
離れて暮らしていても、じいちゃんは俺のじいちゃんだ。俺の雰囲気を察したのだろう。黙って畑のベンチに腰を掛けた。
俺もじいちゃんの隣に座った。あの日と同じように……。でも、何をどう話せばいいのだろう? 長い長い沈黙が続いた……。
「じいちゃん、俺、何もかもが分からんくなった……」
俺が口を開くまで、ずっと口を閉ざしたじいちゃんが、ようやく俺に語り始めた。
「なぁ、三縁。お前くらいの年格好で、分かることの方が少ないと思うぞ。何があったか知らんがの。最近、お前らしくもない書きようだな? 綺麗にまとまっちゃいるが、ツクヨのお話の時のような、間とか勢いってのが感じられん。じいちゃんは、それが、とても気になっとるがのう……」
「そ、そうなの?」
じいちゃんの言葉が胸に響く。何もかもが、見透かされてる気分になった。
「じいちゃん、ブログのことは素人だけどな。今のお前のブログは、農薬と化学肥料で作った野菜みたいな感じがする。小綺麗なだけで勢いがない。三縁よ、あれ、楽しんで書いてないじゃろ?」
図星だった。
「ワシには、そう見えるんじゃ。元を正せば野菜も草じゃ。何もしなくたって、野菜は勝手に育つもんじゃて。土や虫や自然の力を借りての。それが野菜の才能じゃ。自分を信じて自然に任せろ、ワシの孫!」
そう言って、俺の背中をポンと叩いた。
あれだけ頑張って、この評価なのか……。てか、じいちゃん。俺のブログ……あれからも、こっそりチェックしてたんだ。うれしいやら、恥ずかしいやら……。でも、ありがとう。元気出た。俺も草になるわ、鬱陶しいくらいの雑草にな!
オッツーの言うとおり、じいちゃんに話して正解だった。ようやく、いつもの調子が戻ってきた。穫り頃の秋ナスに、芽吹いたばかりの大根に、温存しているさつまいも。そして、新たに植え替えたよつぼし苺……周りの風景に色が戻った。
───テテテテテ。
聞き慣れた足音が近づいてくる。あの足音はツクヨか?
「とおりすがりのツクヨさんですよぉ~(笑)」
やっぱり。
甲高い声に振り向けば、ニヤニヤしながらランドセルを背負ったツクヨ様が立っていた。お前、こんな時間まで何をやってんだ? アヤ姉が心配するだろ?
でも、ふと気になったんだ。ランドセルの横から飛び出したリコーダーが。俺にもそんな時代があったよなぁ……。そうそう、結局、桜木はリコーダーを手に持って登下校してたっけ。
「サヨちゃんのお話、最近、全然、面白くない。どうしたの? ふつうじゃん! わたしのオッツーが心配してたぞぉ」
ツ……ツクヨ、お前もか! てか、わたしのって……。オッツーは俺の同級生だぞ。わたしのと言う前に「くん」とか「さん」とか、付けてあげてはくれないか?
「お前は、オッツーと仲良しだな」
「うん!!」
ツクヨは真っ直ぐな笑顔で返事した。まだ、ツクヨの話は終わりではなかった。ツクヨは自慢げにスケッチブックを広げて見せた。
「ツクヨね、サヨちゃんに絵を描いたんだ。見てみて、これって、凄くない?」
───控えめに言っても、こりゃ凄い! あの下手っぴだった野菜の絵から数年で、ここまでの進化を遂げられるものなのか? 継続は力なり……その領域を軽く超えてる。お前、やっぱり天才なのか?
「ツクヨ画伯。一体、これは何の絵ですか?」
「旅乃琴里先生の“ブログ王”でしたっ! 知ってるよ、サヨちゃん、凄いお話書いてるんでしょ? 小説ってぇーの? それは、桜木君に教えてもらったんだ。でね、みんなが、それを本にしてくれるんだって。アケミちゃん、BLの本。学校に黙って売ってるんでしょ? 闇バイト?」
随分と聞こえの悪い質問だな?
「だから、サヨちゃんの本は私が作るんだって、アケミちゃんが言ってたよ。だから、わたしも協力するの。これは、サヨちゃんの本の表紙になるのだ。ねぇねぇ、BLってなぁ~に? アケミちゃん、教えてくれないのぉ」
俺もBLなど知らん! ツクヨがもう少し大きくなってからアケミに聞け。でも、ありがとな(笑) アケミの良心にも感謝する。
俺は小説に腰が引けていたようだ。ルールもクソもありゃしねぇ。俺はブログで小説を書く。そう決めた。そして、桜木との最後の決戦に挑むのじゃ!
「三縁よ……」
帰り際、じいちゃんが俺を呼び止めた。
「本当にあの子がワシを必要とした時、ワシはあの子の側にいてやれなんだ。ワシは今でもそれを悔いている。お前はワシらとは違う。時間があるんじゃ、たっぷりとな。だから、今じゃなくてもいい。お前の本を完成させて、あの子の所へ行ってやれ!」
そう言ってじいちゃんは、俺に採ったばかりの野菜を持たせてくれた。じいちゃんとさくらさんの間には、もっと深い何かがあったのかもしれない……。ツクヨの手を引く帰り道、俺はそればかりを考えていた。スマホを開くと、のんからメールが届いていた。
見慣れたはずのメアドが愛おしく見えた。

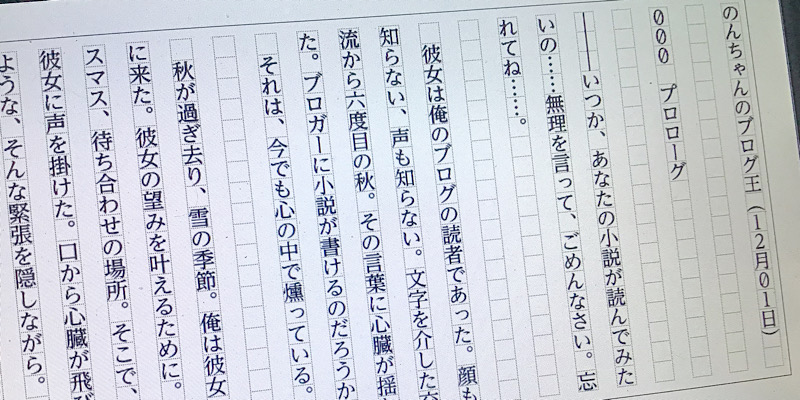





コメント