022 手紙
───俺の小説が、みんなに認められた!
喜びに酔いしれている俺を置き去りに、アケミは次のステージへ進んでいた。
「もう、何、言ってんのよ。遊んでる暇なんてないのよ。これからが忙しいの! 入稿準備よ、入稿準備! もう、あんた、分かってる?」
分かってない。
「はい、みんな。赤入れ原稿見せて!」
不安げな俺に向かってアケミが怒鳴る。
「サヨちゃんは、邪魔!」
荒げた声に感動の涙が引っ込んだ。これから何が始まるというのだ? この場面にBGMを流すなら、運動会の“クシコス・ポスト”あの曲だ。赤組がんばれ、白組負けるな! もう、これはリレー直前の様相である。
「これから何やんだよ、アケミ?」
俺の素朴な質問だ。
「だ・か・ら、さっき言ったでしょ? 入稿準備、入稿作業よ。その前にやるのがチェック作業よ。まだ、終わってないの! わたしらは、これからなの!」
そうなん?
「あんたさぁ、これ、どうするつもりだったのよ? まさか、誤字脱字だらけの原稿で本にするつもりだったとか……バカなの? 嘘でしょ?」
バカだけれど、嘘じゃない。
でも、それを言い出せる雰囲気でもない。アケミの剣幕がそれを物語っている。審査側の三人は、四つの机を合体させて何やら会議をし始めた───ホームルームか?
12月の夕暮れ時。
若さの熱波は、冷えきった教室の空気を吹き飛ばす。吹き飛ばされたのは、俺もオッツーも同じであった。
「ふたりとも、邪魔だから私の視界に入らないで、絶対よ!」
アケミが俺たちに怒鳴り散らす。俺とオッツーは、教室の一番後ろの席に追いやられた。さっきまでの感動は?
「それにしても……多いわねぇ。これ見てよ、誤字脱字。これ、直すの大変よ」
アケミの愚痴が止まらない。これだけで、何かごめんの気分になる……。
「ですわねぇ。ひとつ前のは、そうでもなかったのに。誤字脱字は逆戻りですわ。あー、わたし、ペペロンチーノが食べたい」
相も変わらず、マイペースなのはゆきである。
「私も食べたーい。帰りにパスタ屋、寄って帰ろうね、ゆきちゃん」
「いいですわねぇ。寄ろう、寄ろう」
帰りの予定が決まったようだ。
「……あっ!」
思い出したように、アケミが俺に向かってまた吠えた。
「サヨちゃん! ツクヨちゃんの絵があったでしょ? ブログ王の。あれ、借りてきて。本の表紙に使うから」
「御意!」
我ながら素晴らしい返事だ。しばらく、俺はアケミ様の奴隷だな……。
「あの子、天才よねぇ。末恐ろしいわ……。今ね、私のBLの表紙絵を描いてもらってんだ」
知ってる。
「12月は同人のビックイベントがあるから、サークル活動も忙しいのよ。サヨちゃん、わたしの新作を読んでみる?」
いや、それは……。
「人生観変わるわよ。私の『もう、お前のアレなしでは生きてゆけない』これが、最高傑作なんだわ! 激しいのよぉ~もう、これがっ!」
これって何だよ?
俺は急にツクヨの身を案じた。小学生のツクヨにはまだ早い。アケミの小説で、何が展開されているのかは知らんけど。
「頼むからやめてくれ! ツクヨをお前の世界に巻き込まんでくれないか? 叔父として容認できん! アケミ、どこまでツクヨに教えた?」
アケミが少女の顔で頬を赤らめた。
「そんなの言えないわ……ポッ♡」
なんでなん?
にぎやかな女子を尻目に、桜木は終始無言だ。一分一秒もムダにはしない。そんな意気込みがビンビンと伝わる。いつもは静かで穏やかなのに、声を掛けるのも憚られる。桜木の原動力は何なのか?
「サヨちゃん、時間がないわ。グループワークを使うわよ! 赤入れ原稿を修正したら、グループワークに放り上げて。その後、全員で再チェックを重ねるからね!」
お前の原動力は、何となく分かるけど。
「御意!」
グループワークとは、オンラインで情報を共有するサービスだ。グループ参加者は、情報への加筆修正の権限が与えらる。リアルタイムでの同時作業が可能なのだ。俺たちは長年の付きあいだ。阿吽の呼吸で作業をやってのけるだろう。
桜木は青、アケミは黄色、ゆきはピンク。修正箇所は、マーカーで印を付けるルールになった。だが、俺とオッツーの色はない。それが少し寂しいけれど……。
「サヨちゃん、最初の入力ミスったら……殺すわよ!」
「御意!!」
この日から、俺はアケミの奴隷に徹した。
アケミの指示に従い原稿を修正し、俺は修正原稿をグループワークにアップした。その途端、文字の羅列が生き物ように変化する。数日間、俺の原稿にマーカーラインが引かれては消えた。そして、最後まで残ったピンクのラインがなくなると、アケミからのメールが入った。
───これで、そこそこイケるっしょ! お疲れにゃん。念のために、校正AIチェックも通しといたから。
翌日の昼休み、アケミが俺の教室に現れた。
「昨日で作業は終わったわ。最終データを印刷会社に回したから。サヨちゃんにメールで連絡があるからね。本は自分で取りに行くのよ。自分の本はシビれるわよぉ~。一生に一度だけよ、処女作の快感を味わえるのは」
アケミが俺に微笑んだ。達成感に満ちた笑顔だった。
「ところで代金は、お幾らほどで?」
俺は、それが気がかりだった。
「ハードカバーなら20万から30万円ってところかな?」
「そ……そんなに?」
アケミはさらりと言ってのけたが、俺は椅子から立ち上がった。
俺の未来の光が消えた。
「嘘よ」
よかったぁ~、心臓が止まるかと思ったぞ。アケミはこんなところが悪趣味だ。
「話はついているから1万円だけ持ってって」
俺はアヤ姉からのお駄賃をパソコンの購入資金として貯めていた。30万は絶望的だが、それくらいなら大丈夫。
「それと、あんたのおじいさんに感謝するのよ」
「じいちゃんが?」
じいちゃんて?……俺は理由を知りたくなった。
「本を受け取りに行けば分かるわよ。口止めされてるから、おじいさんに聞いちゃダメよ!」
俺はアケミに言われるがまま、おとなしく印刷会社からの連絡を待った。
───数日後。
昼休みに、印刷会社からメールが入った。会社名はエアメール。
その日の放課後。俺はエアメールに立ち寄った。俺の町では、誰もが知ってる大きな会社だ。
「あの……飛川ですが……」
「お話は聞いています。しばらくお待ちください」
受付の女性が事務所の奥へと姿を消した。受付で立っているだけで緊張する。
「来たか、来たか、いらっしゃい」
ぽっちゃりとした白髪の老人が、ニコニコ笑顔で俺に三冊の本を手渡した。白い髭が印象的だ。
「うわぁ、本だ!」
俺の脳がバズって感動よりも驚きだ。ハードカバー、ツクヨのイラスト、美しく並ぶ文字……具現化した願望に、俺はブルッと身震いした。これが、処女作の快感……アケミの言ったことは本当だった。
「待っていたよ。君が、飛ちゃんのお孫さんかい?」
ここは小さな田舎町である。この老人がじいちゃんと知り合いでも、誰も不思議だとは思わない。
「はい。そうですが……」
「そうか、そうか。飛ちゃんの孫が小説を書くとは……血は争えぬということか。親友の孫やからの。製本代金は大サービスじゃ」
やっぱり、じいちゃんも小説を……。
「アケミが……いや、僕の同級生が、普通なら30万円くらい必要だとか言ってましたが……本当に1万円で大丈夫ですか?」
立派な本を手にすると、やっぱり代金が気になった。
「今のワシと会社があるのは、君のおじいさんのお陰でもあるからの。もし、チラシ印刷だけなら、おじいさんの本を作らなければ、この会社はとうに倒産しておった。ここで初めて製本したのが、おじいさんの小説だったんじゃ」
老人は、懐かしそうな顔で微笑んだ。
「これは、ワシから飛ちゃんへの恩返しでもあるんじゃよ。ワシを誰だと思ってる? この会社の会長じゃぞ! わっはっは」
俺の前のカーネル・サンダーズが豪快に笑った……てか、会長さん?
「まぁ、こっちに入って、入って」
俺は応接室に通された。高級そうな本革製のソファーに座ると、ツクヨがお茶を持ってきた。
「おま……何やっとん?」
俺は驚きを隠せない。
「わたし、ここでイラスト書いてるの。社長さんから、サヨちゃん来るよって聞いたから。遊びに来たの」
ツクヨの絵に惚れ込んだのは、この会社の社長さんだったのか……。って事は……会長さんは、オトンとも繋がってる? だからといって、こんな破格値にはならないだろう。
「じゃ、サヨちゃん。がんばってね」
ツクヨはぎこちなくテーブルの上にお茶を置いた。そして、ペコリと頭を下げてから、テテテテテと応接室から出て行った。
「飛川君。おじいさんの文通相手の話は知ってるか?」
会長さんが、俺に話を切り出した。
「はい。さくらさんの話ですよね?」
俺は答えた。
「でも、おじいさんが小説を書いた話は知らんのじゃろ?」
会長さんは、俺の顔を覗き込んだ。それは、俺が聞きたい話でもあった。
「はい。それは話してくれませんでした……」
この人は、じいちゃんの小説を知っている。俺はソファーから身を乗り出した。
じいちゃんの話には続きがあった。封筒の中には、二通の手紙があったのだ。ひとつは、さくらさんの訃報を告げる母親からの手紙。もうひとつは、さくらさんからのお別れの手紙。
───いつか、小説を書いてください。
さくらさんの願いは、じいちゃんが書いた小説を読むこと……それがのんと重なった。働きながらじいちゃんは、何年も掛けて小説を書き上げた。そして、本にした。決して彼女の元には届かない。二冊だけの本だった。
多かれ少なかれ、小説の中には現実の影が紛れ込む。亡き人を偲びながら、どんな気持ちで書いたのだろう? それが、今の俺には理解できる。彼女との思い出を胸に、心を引き裂かれながら書いたのに決まってる。
「ありがとうございました……」
あの日───じいちゃんが口を濁した現実に、俺の目から涙が溢れた。初対面の会長さんの目の前で、俺は子どものように泣きじゃくった。
「君の小説、なかなか面白いじゃないか。サービスの中には購読料と期待料も入っとる。この本は、未来の作家の処女作になるやも……そんな夢まで見せてもらった。こちらこそ、ありがとうございました」
会長さんは頭を下げた。俺も会長さんに頭を下げた。
「ひとつ、教えてもらっていいですか? 今、その本は……」
俺はじいちゃんの本の今を知りたくなった。
「飛ちゃんの本なら、飛川の家とさくらさんの家にあるはずじゃよ。たとえ孫でも、あいつが素直に読ませてくれるとは思えんが……」
いつの日か、俺はじいちゃんの小説を読みたいと思った。そして、ふたりの物語を書きたいと思った。じいちゃんがいなければ、さくらさんからの手紙がなければ、俺の本の完成はなかった。俺を取り巻く神の伏線。それは、若きじいちゃんから始まっていたのかもしれない……。
───そうだ、俺も手紙を書こう。
これまでの出来事に、心からのお礼を添えて。
俺は処女作とお礼の手紙を箱に詰めた。こんなことも最初で最後だ。下手な文字だけれど許してもらおう。
小包の宛名は旅乃琴里。
小説を書くはずのない俺が筆を執った。彼女のコメントから全てが動き始めた。誠意だけでも伝えたい。とはいえ、相手は雲の上のラノベ作家。俺の小包が届くかどうか? それは全く分からない。それでも俺は構わない。気持ちだけでも伝えたい……それが一番大切だから。
小包の配達指定日は、クリスマスの翌日にした。

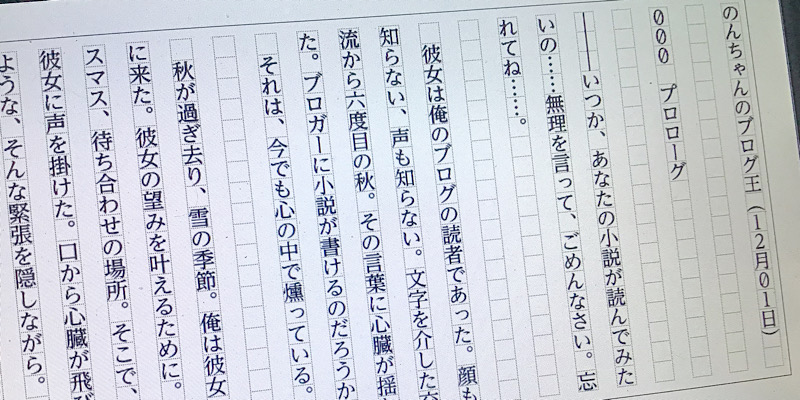





コメント