「これ、可愛いだろ?」
お茶袋を指さして、あいつが俺にそう言った。
茶袋には猫のイラスト。そんなことはどうでもいい。こいつの所へ出向いたのにはワケがある。気になることがあるからだ。あいつが小説を書き始めたらしい……その真相を俺は知りたい。
中学時代、俺の夢は小説家だった。身を削る思いで作品を書いた。それを同級生に読ませると、みんなは俺の夢をバカにした。
「これで小説家になるつもり?」
あいつだけが、俺の夢を応援してくれた。
「いいんじゃね? なれよ、小説家に。本になったら買うからさ。買った本にサインしてくんねぇ~か?」
そう言って笑ってたっけ……。
遠い昔の話だ。大人になった俺は、夢なんてすっかり忘れて、本すら読まない大人になった。あいつの噂が、忘れた想いを呼び覚ます。けれど、あいつと小説との接点が分からない。あいつの不得意教科は……国語だった。
「読書感想文を書くくらいなら、死んだ方がマシだ! ちょっくら今から、担任のお説教を受けてくらぁ~!」
俺にそう言い残すと、あいつは職員室へ向かって歩いた。その後ろ姿を思い出す。そんなあいつが……小説だって? それだけは、どう考えてもあり得ない……。でも、あいつが書くと言うのなら……。
「ほれ、お茶だ。お茶しかねぇ~けど、飲んでくれろ」
あいつがお茶を差し出した。お茶なんてどうでもよかった。俺はお前の心境の変化を知りたいんだよ。俺の夢をあいつが……何故だ?
「お前、小説を書き始めたそうじゃないか?」
そう切り出すと、あいつの顔から笑顔が消えた。
「まぁ~な……」
そう言ってお茶をすする。自分から語り始める気配など微塵もない……長い沈黙が続く。どういうワケだか、俺はイライラしていた。俺が諦めた夢をお前が追うのか?
「お前、作文なんて嫌いだろ? それがどうして、その気になった?」
「仕方ないからだ。書きたくて書いてるわけじゃない」
書きたくて───だって? それが俺の地雷を踏んだ。そう……俺が小説家を諦めたのは、お前の落書きを読んだからだ。遊びで俺がお題を出して、あいつに書かせた物語。A4用紙一枚分の文字の列。俺はそれに魅了された。続きが読みたい……そう思わされた。俺には到底届かない、その領域にあいつはいた。そのとき俺は心の底から嫉妬した。殺してやりたいほど嫉妬した。狂おしいほど嫉妬した。そして俺は小説を……諦めた。
「そんなの、小説に対する冒涜だっ!」
俺は俺の持ち得る語彙を駆使して、あいつにわめき散らした。一瞬、あいつはたじろいた。だが、何事もなかったかのように、あいつは平然と口を開いた。
「小説に、オレの命くらいなら削ってもいいかな? 今は、そう思ってる」
それがあいつの答えだった。お茶の袋を指で撫でながら、あいつは俺に言う。
「オレは命をかけられたんだ。だったら、命くらい削らないとな……」
どうなれば……そんな哀しい目が出来るのか?
「お前……何があった?」
「大した話じゃない。オレの文章を気に入ってくれた人がいて、そいつに『小説書かない?』って誘われただけだ……」
あいつは俺と目を合わさない。俺の夢を知っているから、気まずく思っているのだろうか? ずっとあいつは、お茶の袋を愛でている。
「その先があるだろ? その程度で腰を上げるお前じゃない」
そう。あいつは、その程度で筆など持たない。
「そいつ病気でさ……星になっちまった。もう、長くないことは分かっていたんだ」
そう言いながら、お茶の袋を見つめている。惚れた女でも見るような……愛おしそうな目をしながら。
「そいつがさ、このお茶を持ってきたんだ。ほれ、イラストの横に手書きの文字があるだろ? もらったお茶の全部にメッセージが書き込んであった。概ね、オレの小説が読みたい的な……残った二袋をオレとお前とで飲んでいる。つまり、これが最後。ありがたく……飲めや……。オレはお前が来るのを待っていた」
そう言って、あいつはお茶を口に運ぶ。あいつの袋には〝月がきれいですね〟と書かれていた……もしかして……漱石か?
「それと執筆と関係あるのか?」
俺は問う。
「大ありだ」
あいつが答える。
「あいつが来たとき……コロナのど真ん中でな。入院してたのに外出してさ……このお茶をオレに持ってきたんだ。後で知ったけど、かなり病状が悪かったらしい……それが、あいつと顔を合わせた最後だった。オレはあいつに何もしてやれなかった。何ひとつ……してやれなかった。だから……小説くらい書こうと思った……もう、遅いけどな」
「お前はプロになるのか?」
俺の心がざわつき始める。あいつの答えを聞くのが怖かった。でも、知らなければならない気がした。知らない誰かに背中を押されたような……気がした。
「うんにゃ、分からん。そこまでは考えてない。オレの小説で、あいつが笑ってくれるだけでいい。それがいい」
俺は思う。小説は……そんな甘い世界じゃないのだと。
「その程度の気持ちで、小説が書けるとは思えないのだが?」
茶袋の文字を眺めていた目が、鋭い視線で俺を睨む。その眼光に、俺は背筋に冷たさを感じた。
「いいんだよ、書けなくても。あいつは……ある意味、命がけだったんだ。命をかけてオレの所へ来たんだ。命をかけたメッセージを受け取らない道理があるか? もしもオレに、そんな才能があるのなら、オレの命くらい削ったって───罰なんて当たらねぇ。だから書いてんだよ。オレにはそれしかないんだよ。それしか能がねぇんだよ。こっちは好きでやってんだ。さてはお前、嫉妬してんのか? 小説を書き始めたオレに」
図星だ……。俺は核心に触れたくなった。
「で、どこまで書いた?」
「あ、ちょっと待っ……」
あいつは思い出したように、黄色い付箋に赤ペンで何かを書き殴って壁に貼り付けた。今まで気づかなかったが、部屋の壁の至る所に付箋が貼り付けられている。書かれた文字は文章ではない。名前、単語、動詞、形容詞……一枚の付箋に数個の単語があるだけだ。覚え書き?……そんな感じだ。ペタリと付箋を貼り付けると、あいつはノートパソコンを取り出した。
「読むか?」
「当然だ」
あいつのノートにあった文章は、ある意味で殴り書きだった。荒々しい文章がファイルの中で荒れ狂っていた───圧巻だった。ただ、順不同なのが気になった。
「どの順番で読むんだよ、これ?」
「さぁ、分からん」
ひとつ、ひとつの話が完結している。フォルダの中はショート・ショートの塊だった。これが一本の小説になるのか? それとも、それぞれが完結しているのか? でも、これは……きっと一本の小説なのだろう。網膜に投影済みの文章に嫉妬する。あの日と同じ敗北感……。
「さっき、お前。俺に言ったよな? 俺が来るのを待っていたって……」
「ああ、きっと来ると思ってた」
「何でだよ?」
「それがお前の夢だから。で、俺の文章───どう思う」
あいつからの質問に率直に答えよう。癪だけど……。
「文才が山手線を暴れてた……かな?」
あの時と同じ気分だよ……思い出したくもない苦い思い……まったくな。
「で、小説って……どう書くんだ? オレが書いているのは小説なのか?」
照れくさそうにあいつが言った。
「そこからか? そこから話さないとダメなのか? ……まぁ、これは……」
「……」
あいつの言葉に俺は察した。こいつは何ひとつ理解していない。ただ、がむしゃらに書いているのにすぎなかった。筆を持った暴れ馬。でもこれは小説だった。俺を引き込むほど小説なのだ。やっぱ、こいつは天然の天才だ。己の劣等感と執着心。それがバカらしくなった途端、俺は腹の底から笑いが込み上げた。さしずめ笑いの鉄砲水だ。
「紛れもなく───小説だ!」
爆笑しながら俺は答えた。腹が痛い……でもそれは、神に誓って噓偽りなき答えだった。
「そっか……よかった」
安堵の表情を見せた後、あいつの雰囲気が重くなる。これから決定的な何かが飛び出す……そんな予感。長年の付き合いだ。それくらいなら俺にも分かる。シュッと俺は背筋を伸ばした。
「なぁ……オレの小説、手伝ってくんね? ほら、オレ……死ぬほど作文が嫌いなんだよなぁ~。国語も知らんから、何を書いてるのかもよく分からん。今日みたいに、読んだ感想だけでもくれると助かる」
あいつと過ごした中学生時代。その場所に舞い戻った気分に俺はなった。ふっと、懐かしの教室が脳裏をかすめる。この気分は悪くない。
「お前に小説を書かせたお茶の人。控えめに言っても凄い人だな……でも、言っとくわ───すまんな! 先に謝っとく。これから、変な質問をお前にする」
俺は、単刀直入にあいつに訊いた。
「その人、お前の彼女か?」
「うんにゃ~」
あいつに上手くかわされた感じがした。
「そっか。でも、大切な人なのか?」
「そりゃそうだ」
うーん……。お前が作家を目指すなら、手を貸さないこともない。少しだけ、俺は失くした夢を見始めていた……。
「俺、これから仕事なんだわ」
「あぁ、すまんすまん。ついついお前に身勝手を言っちまったな。いつまでも中学生とは違うもんな。奥さんと娘ちゃんによろぴくな。今日のことは忘れてくれろ」
あいつは頭を掻きながら、照れくさそうに謝った。帰り際、俺はあいつに言った。
「お前の文章はスゲーけど、お前の日本語は無茶苦茶だ。明日の夜から空けとけよ───これから長丁場になるからな。覚悟しとけ。その暴れ馬、調教できるのは俺だけだ!!」
俺とあいつの中二病。それが再発したようだ。家で嫁と娘に謝らないといけないな……。でも俺は、お茶のキミに感謝している。あいつを覚醒させてくれたのだから。その行く先を天国から見守っていてほしい。
中二病、バカふたりの行く末を。

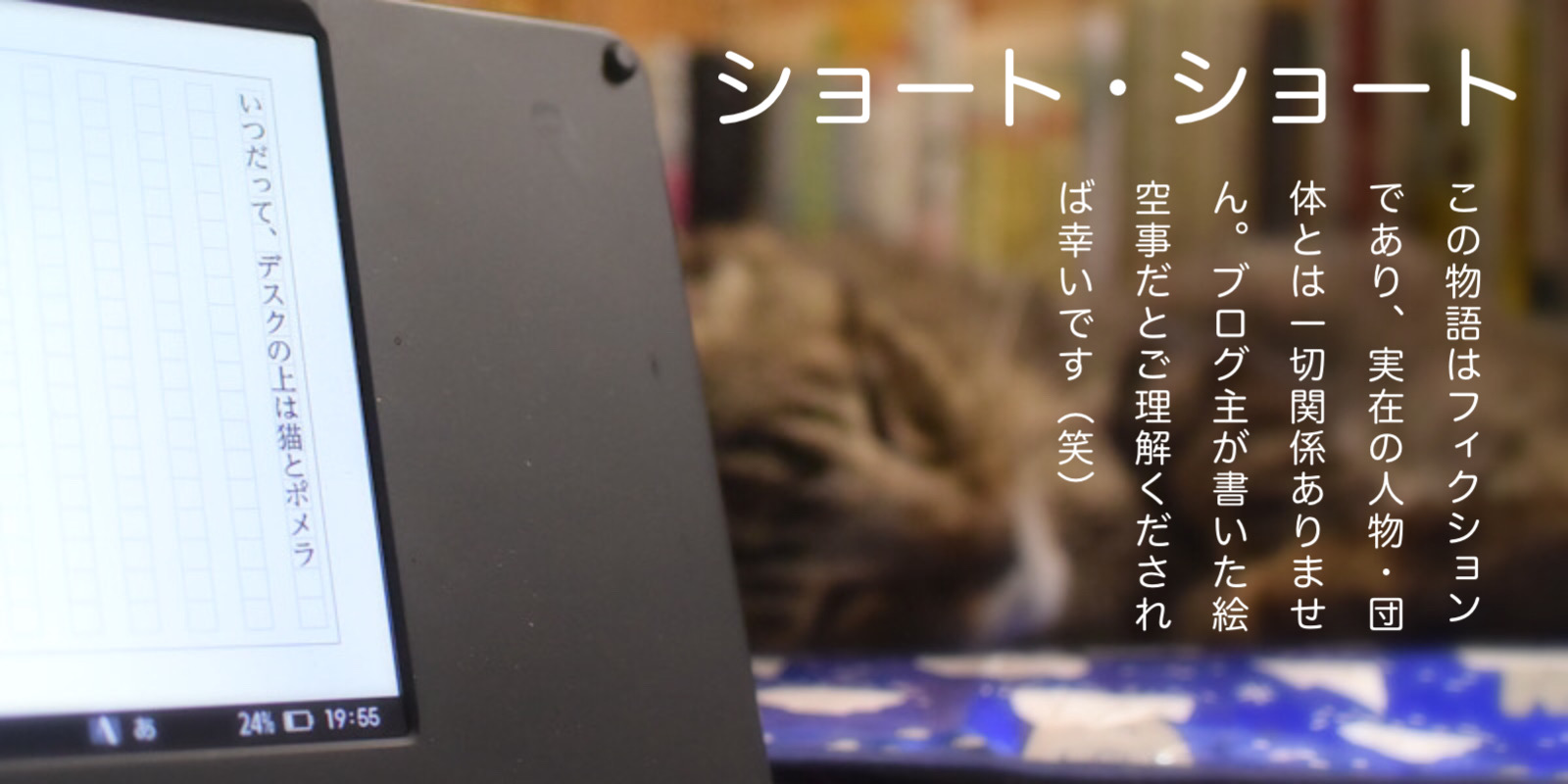

コメント