目立たたない人がいる───あれ、いたの? な体質の人。オレもそんな人間だ。ただ違うのは、オレの存在が極端に認識されないことである。透明と言えば聞こえもよいけど、無味無臭な透明人間となれば話も変わる。
いつもそう、いつだってそう。オレの名が認識されても、そこにオレがいると認識されない。厄介なことに、その理由がオレにも分からない。気配を消しているワケじゃない。むしろ……その逆。だから話をややこしくさせてしまうのだ。仲間との会話に混ざって発言だって抜かりないのに、後になって「あれ、いたの?」とは些か悲しい思春期だった。
目立たないオレにだって友達はいる。オレのクラス全員だと言っても過言じゃない。声を掛ければ返事もくれるし、何かの集まりにも呼んでくれる。それなのに、その場にいてもいないことになっているのだ。ちょっとしたホラーな話になるのだけれど、高校時代にこんな話があった。
オレは剣道部に所属していた。部員全員が顧問の先生に引き連れられて、向かった先がファミレスだった。真夏の体育館で防具を付けた練習は、さしずめサハラ砂漠でランニング。全身汗だくでパンツまでビショビショ。その後での乾杯である。それぞれが、好きな飲み物をドリンクバーで注いだ後、世間話に花を咲かせる。その中にもオレはいた。冷房が効いた店内で、先輩たちとも楽しく話した。異変に気づいたのは会計の時である。当然、お勘定は顧問が支払う───当然だ。
「おい。今日、誰か休んでいるのか?」
顧問が首をかしげる。お会計が9人分なのだ……ひとり足りない。剣道とは武士道である。たとえ利になろうとも、曲げてはいけないことがある。人の道に反することだ。顧問は店員に確認をする。
「申し訳ないのだが、ひとり分の勘定違いをしていませんか?」
店員は胸を張ってはっきり答えた。
「9名で間違いありません。私、キチンと数えました。後からどなたかお見えになりましたか?」
と言い切った。私、間違ってないもん! 一歩も引かない形相だった。そもそもだけれど、部員9名、顧問1名。この数は絶対である。なのに、店員の反応に部員どころか顧問までもが自信をなくす。
「あ……そうかもしれませんね。今日はひとり休んでいたのかも……。では、お会計をお願いします」
オレは思う。何度も数え直しても、この場には10人いるのだ。なのに、どいつもこいつも自信なさげな表情だった。
「全員、整列!」
店を出てから、顧問が部員を一列に並べた。そして、指をさしながら数え始めた。
「1、2、3……」
最後に自分を指さして
「10……だよなぁ?」
そう言って首をひねる。パラレルワールドにでも迷い込んだような複雑な表情だった。顧問の狐につままれたような顔に、部員たちから不安の声が上がり始める。
「これ、何かで読んだことがある……俺達の知らない誰かが、この中に紛れ込んでいるんじゃないのか?」
「そんなワケねーだろ? だって、部員9人、顧問1人だから10人だよ。キツネだってそこまでしねぇ~よ」
「だったら、誰かひとりが店員さんに見えなかったってのか?」
「そんなの透明人間じゃん?」
「んな、馬鹿な……」
こんなの真夏の白昼夢じゃないか? 真昼に幽霊なんて出やしない。なのに、ホラー映画の一場面のよう。何度数えても10人だった。どうやっても10人いる。そのまま小康状態が続き、主将が突然声を上げた。
「あれ、いたの?」
それは、オレの人生で何度も聞いたフレーズだった。いやいや……今日、主将さんとも話をしましたって。オレは困惑の表情を見せるのだけれど、部員どころか顧問までもが、今日初めてオレを見たような顔をしている。
「今日、練習に来てたっけ?」
顧問がオレに問う。
「いました。主将とも掛かり稽古しましたけど?」
オレは少しトサカにきていた。あれだけ話をしておいて、あれだけ竹刀を交わしておいて、透明人間扱いだなんて───失礼にもほどがある。オレの怒りなど構わずに、部員全員がオレを見る。顧問の青ざめた顔にはうんざりだ。そういうの……もう、飽きた……。
「今日、いた? 休んでなかった? でも、ある意味でお前スゲーな! 気配ゼロにできるのな。お前の前世って、忍者だろ?」
先輩のひとりがオレをからかい始めると、全員がそれに乗った。もう、そんなの慣れっこだけれど、洞爺湖の木刀で殴ってやりたい気分だった。そして、先輩の口から飛び出した一言がオレの地雷を踏み抜いた。
「ところでさ、お前の名前って……何だっけ?」
オレの手がパーからグーへと変化する。指の爪が手のひらに食い込んだ。じっと堪えて返事を返す。
「キセです!」
このままオレは、一生、透明人間扱いをされるのか? 不安を飛び越し恐怖を感じる。社会人になって就職しても、オレ……営業とか無理っぽい。高校生活の三年間、オレの透明度はサルガッソー海そのままだった。オレの透明度で船も浮かんで見えるだろうよ。
───透明人間
オレのコンプレックスを一変させたのが、大学で出会ったアカギだった。太陽のように明るいアホだ。不思議なことに、アイツといるとオレの存在が認識される。アイツがいないと今までどおりのサルガッソー海に戻るのだが……。オレはそれが不思議だった。それをアイツに聞いてみた。アイツの見解を知りたかった……自他ともに認める野生のアホな男だけれど。
「そりゃ、オメェ。俺様がお天道様みたくギラギラ輝いているってことじゃねーの?」
やっぱりコイツはアホだった……。。
「どういう意味だよ? アカギ」
「だって、そうだろうが。俺にはお前がはっきり見える。もし、お前が俺を太陽だって思うなら、俺の光を反射して、オメェの姿はでっけぇ~満月の形になって、みんなに見えてるってことだろ?」
「ん?……うーん……」
根拠なきご駄句を並べて話すアイツ。なのに、妙な説得力がアカギにはあった。覚えておいてもらおうか。オレの名前は黄瀬学公だ。早ければ半年後、みんなの前に再登場するだろう───アカギに強烈なツッコミを入れながら「あれ、いたの?」というキャラにも磨きをかけて(笑)

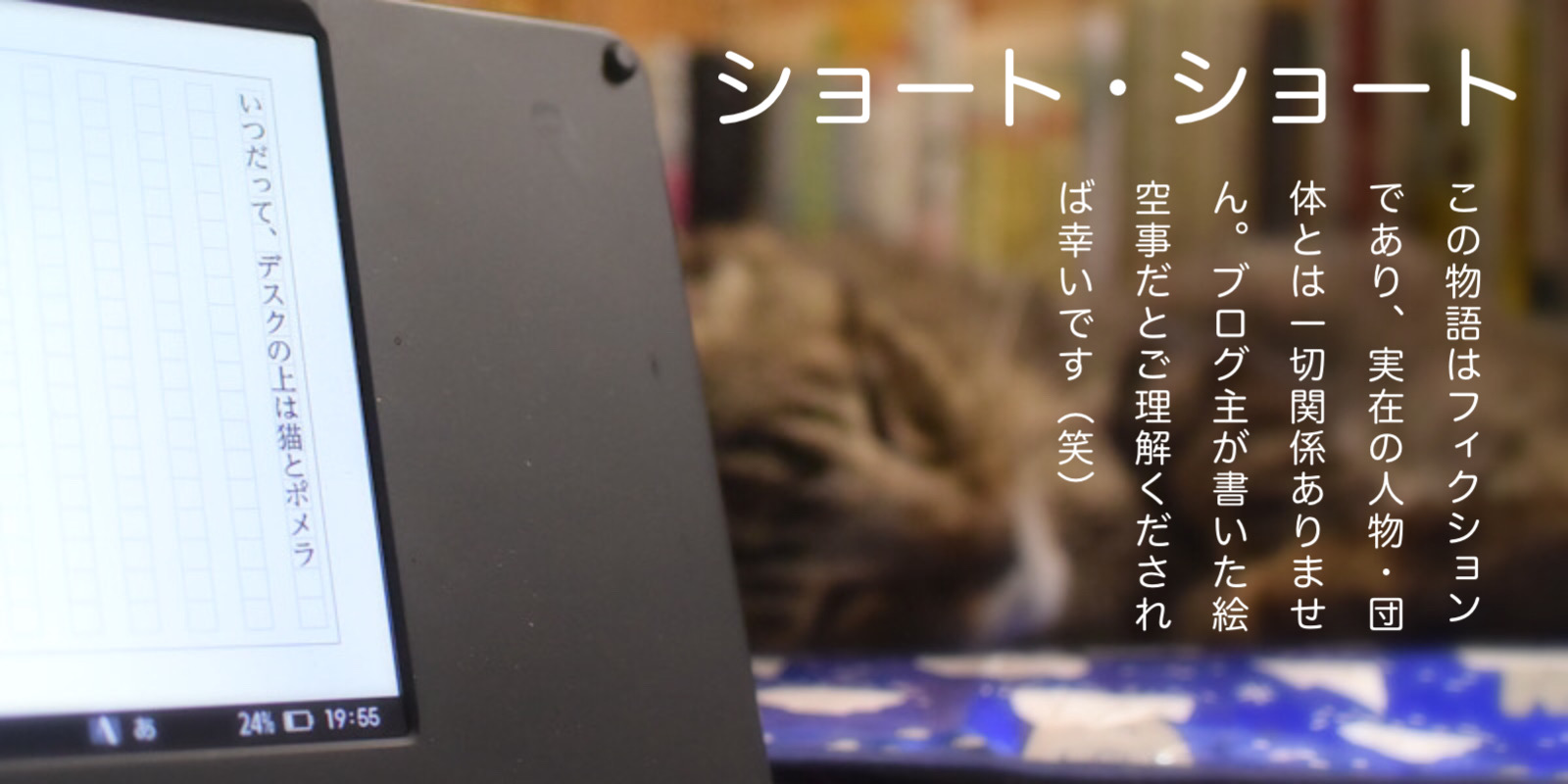

コメント