午前零時……死神チハルが仕事から戻ってきた。
「おっじ、さぁーん! 私はお腹が空いているのですよっ(笑)」
いつもそう、いつだっそう。チハルは窓から飛び込んでくる。
「なぁ、チハル。ただいまは?」
「そうでした。ただいまでしたね。ただいまチハルは戻りましたですよ、へへへ」
チハルは反省したような声で言ったけれど、満面の笑みが全てを物語っている。つまり、チハルは反省などしてない……。
「なぁ、チハル。それそろ玄関から入ってくれない? 急に窓から入ってくるの、毎回ビックリするんだけどなぁ……」
「ビックリはしないでしょ? 窓から隣の女の子が入ってくるのは、少年漫画の定番ですよ」
いやいやチハルちゃんよ、現実は漫画じゃないし。普通、誰だって驚くから!
「ここは私の家ですよ。自分の家に何処から入ったっていいじゃないですかぁ? 私は窓からがお気に入りなんですよ、へへへ」
どういうワケだか、チハルは玄関から入ろうとしない。前世の記憶が無いのだから、無意識でそうしているのだろうけれど。それにはきっと、深い理由があるのだろう……な。
「はい、はい。今夜はハンバーグでよろしいかね?」
ハンバーグはチハルの好物である。一番好きなのはエビフライだけれど、理由は知らない。
「分かってますねぇ、おじさんは。私、今日はハンバーグの気分なのです。ハート型とかにできますか?」
「チハルの頼みだからな、やってみるさ」
「そのセリフ。私も知っていますよ、シャア少佐。ぜひとも、ハートのカタチでお願いします! ちなみに私はヨッちゃん派ですよ」
てっきり俺は、チハルはマッチ派だとばかり思ってた……。
「そっか、俺は聖子ちゃん派だけどな」
「へへへ。私と同じ髪型ですね」
お前が聖子ちゃんと同じ髪型だろ? チハルは自分の髪を撫でながら続けて言う。
「おじさんは、ぶりっこがお好みなんですね。てっきりミーちゃん派だとばかり思っていましたよ」
「それ、ピンクレディな。芸能界のモンスターも解散ちゃったけどな」
「ぎょえぇぇぇぇ!!!! 普通の女の子に戻りたいですか?」
チハルはクリっとした瞳をパチクリさせた。一応、この場はツッコんでおこう……。
「それ、キャンディーズな」
今夜のチハルはいつもと違う。
仕事から戻ると、いつも不機嫌な顔なのに……今夜のチハルは上機嫌だ。だって、そうだろ? チハルの仕事は死神である。死を看取るのが仕事なのだ。笑って帰る方がどうかしている。その心中を察して、これまで俺は何も聞かずに過ごしてきた。チハルが口を開くまで。
「今日のご飯は不要ですよ……疲れたので、おやすみでした……」
そう言い残すと、いつもチハルは寝てしまう。
チハルは仕事が終わると食事を取らない。酷ければ数日の間、一切の食事を取らなくなる。彼女曰く、死神は食べる必要などないのだそうだ。生きている人間の真似事をしたいから、ご飯を食べるのだとチハルは言う。だが俺は、俺の料理を食べるチハルの顔が好きだった。カレー、チャーハン、ビーフストロガノフに納豆ご飯……何を作っても、それは美味しそうに食べるのだ。あの笑顔をされる気分は悪くない。
「おじさん、今日はとてもステキなことがあったんですよ」
「へぇ、珍しいな。チハルが仕事の話をするなんて……初めてだね?」
そう言って、食事の支度をし始めながら俺は思う。どうやって、お肉をハートの形にしようかね……。
「ねぇ、おじさん。私の話を聞いてくれますか? てか、聞いてくれますよね?」
ホントに今日はご機嫌さんだ。チハルからの問いかけに、俺は何故だか嬉しくなった。
「いいぞ、聞こうじゃないか。苦しゅうない! しっかりと存分に話せ」
俺はミンチ肉をこねながら、チハルの声に耳を傾けた。男のくせして、チハルの母親にでもなった気分だ。
「エッとですね……今日はご老人のお迎えに参ったのですよ。私は胸がキュンキュンしちゃいましたよ。へへへ」
うさぎが飛び跳ねるようなチハルの声が、俺にはとても心地よかった───ジジイにでも……惚れたのか?
☆☆☆☆☆☆☆
───1982年9月1日22時56分38秒。市民病院307号室。
心電図の音だけが病室の中で響いていた。白いベッドに横たわり、老人が最後の時を迎えていた。その姿は、寿命というより病気であった。人の命の終わりの瞬間……その光景にも慣れたチハルは、淡々と業務に入る。まずは、マニュアルどおりの自己紹介と本人確認からである。
「初めまして、私はチハル。人間から死神と呼ばれる存在です。あなたのお迎えに参りました。もう少しだけ、現世でのお時間がありますけれど。正確には、23時03分12秒がお迎えの予定時刻です。あなたは、山本修二さんで間違いないですね?」
これが、いつもの第一声。チハルを見ると、見た者は全て怪訝な面持ちになる。その後で、決まってチハルに不平不満や後悔の念をぶちまける。その場で泣き叫ぶ者も少なくはない。きっとこの老人もそうなのだろう……チハルは、それがとても嫌であった。でもこれが、神様から与えられた己への罰だと信じ、チハルは死にゆく者の言葉を聞く。だが今日は、いつもと勝手が違うようだ……。
「おや? 私の知る死神とはまるで違うお姿ですね。人生の最後に可愛らしいセーラー服のお嬢さんが、私のお迎えにくるとはね……そうだよ、お嬢さん。私が山本修二です。この度はお世話になります」
いつもなら、何で? どうして? 死にたくない! 死神───帰れ! そんな罵声を浴びせられるのに、老人の声は穏やかだった。
「何かお話することはありますか? 私は黙って聞くだけですけど?」
これもマニュアルどおりの対応だ。死者の魂を落ち着かせるのも死神の仕事である。
「そうかい? 私にはね、心残りがひとつだけあるんだよ」
「それは何でしょう?」
老人は、病室の天井を見つめながら静かに語り始めた。
「私を初恋の彼と呼ぶ人がいてね。この十年もの間……食事、散歩、お風呂、トイレ……私は彼女のお世話をしてきたのだよ。私にとって、彼女は初恋の人だったからね。彼女のお世話ができた日々……それはとても幸せな日々だった。でも……もう、私は死ぬのか。愛する彼女を残して死ぬのは辛いね……」
そう言うと、老人は小さくため息をついた。
「とても大切な人なんですね、その方。お気の毒です……」
これはチハルの本心である。
「私の名前は修二だけども、彼女は私を五郎と呼ぶんだ」
思わぬ言葉にチハルは驚く。そして、老人の顔を覗き込んだ。
「ど……どうしてですか? 山本さん」
「彼女は痴ほう症を患っていてね……私を初恋の彼だと思い込んでいるのさ。医者の話では、女学生時代までの記憶しか……もう、彼女には残されていないそうだ。だから、私との記憶は何処にもないんだよ。私の記憶は何もない。最初はとても辛かったけどね。でも……彼女はとても嬉しそうな顔で私を呼ぶんだよ、五郎さんって」
「はぁ……」
チハルは返事に困った……。
「五郎というのは、彼女の初恋の相手だよ。片恋慕だったらしいが、とても好きだったのだろうね……」
つまり……そういうこと? 状況を察したチハルは、もう何も言えなくなった。寂し気に老人は話を続ける。
「五郎さん、今年も桜がキレイねって。五郎さん、今日はお天気ねって。五郎さん、大好きよって。五郎さん、五郎さん、五郎さん……彼女の全てが五郎さんだった。私の名が呼ばれることなど、この十年間で一度もなかった。でも、彼女が幸せなら、あの笑顔に会えるなら。私はそれで構わない。私は彼女の笑顔が見られるだけで幸せだった。そう思いなから、私は五郎を……ずっと演じてきたんだ。本音を言えば、最後に私の名前で呼んでほしかったかな? あっ……そろそろ……お時間ですね。死神のお嬢さん」
そう言って涙ぐむ老人に、チハルは何も答えられずにいた。老人に残された時間は残り1分を切ろうとしている。チハルは老人を見守るだけだ……見守りながら、チハルは腕時計を確認する……そろそろ天井に浮かばないと……。
チハルの体がふわりと空中に浮き上がる。すると、ガシャリと病室のドアが開いた。そして、老人のベッドに老婆が近づき問いかけた。
「わたしの名前を知っていますか?」
老人は驚いた表情で老婆を見つめた。そして質問に答えた。
「幸子だよ。君は自分の名前まで忘れてしまったのかい?」
老人は寂しげに答え、老婆は更に問いかける。
「あなたの名前は何ですか?」
老人は哀し気な目で老婆に答えた。
「何を言ってるんだい? 私は君の初恋の相手じゃないか? 五郎だよ(笑) ずっと、君が愛している……私は初恋の相手だろ?」
チハルは思った……あれは優しい嘘なのだと。最後まで見ず知らずの他人を装い、この世を去るつもりなのだと。チハルは老人の顔を見ていられなくなり、そっとふたりに背を向けた。老婆は老人の手を握りしめ、ムッとした表情で語尾を強めた。
「何を言ってるの! 修二さん!!」
私の名前を? 老人はハッとした。
「私のことが……分かるのかい?」
「分かるも何も、アナタはわたしの旦那様じゃないの! ずっと修二さんは、わたしの旦那様でしょ? 忘れたの?」
老婆は左手の薬指を老人の顔に近づけた。
「ほら……この指輪を交わした日のこと……アナタ忘れちゃったの? わたしの花嫁姿……忘れちゃった? ねぇ、修二さん。ずっとずっと大好きよ。あなたと結婚して幸せだった……」
最後の力を振り絞り、老人は老婆の顔をやさしく撫でた。シワシワになった手のひらに、老婆は頬ずりをしながら涙を流す。幸せを噛みしめながら……。
「ありがとう……幸子……」
老人の顔から笑みがあふれ、その目から涙がこぼれた。
「修二さん、わたしはとても幸せでした」
「私もとても幸せだったよ、幸子。向こうで待ってる……」
それが老人の現世で最後の言葉になった。
記憶を取り戻した老婆に看取られながら、眠るように老人はこの世を去った。チハルは思う。真っすぐに生きた老人へのご褒美に、ひと時だけ神様が老婆の記憶を戻してくれたのだと。
……神様、やりましたねっ!
「では、参りましょう! 今回は、1分だけサービスしました。後で始末書を書かされちゃいますけどね。山本さんにだけ……特別にですよ。それと天国の階段、途中で耳がキーンとなりますよ。だから、耳抜きが必要です。でも、山本さん……とてもステキな人生でしたね。死神のお仕事で、初めて私は感動していますよ。山本さん、カッコいいです。へへへ」
ふたりに背を向けていたチハルは、振り返りながらそう言った。振り返ったチハルの顔は、とても明るい笑顔だった。
☆☆☆☆☆☆☆
歌は歌って初めて歌であり、鐘は叩いて初めて鐘であり、愛は……愛は与えて初めて愛である……か。
───ジュー!!!!!!……あちぃ!
俺はハンバーグを焼きながら、チハルの話に涙ぐんだ。老人の人生に、同じ男として遠い憧れすら感じていた。それは俺にとって、もうあり得ない未来だけれど……。
「おじさん特製、スペシャルハンバーグの準備が整ったぜい!」
湿った空気に、俺は明るい声を出す。
「わぁ~い! ハートだ。おじさんって、天才ですか? シェフを呼べな気分です!」
俺の作ったハンバーグに、チハルは女の子らしい反応を見せた。続けて俺はこう言った。
「今日のデザートはリンゴだぞ。ほれ見てみ? うさぎさんだぞぉ~」
俺はチハルに、うさぎカットにしたリンゴを見せた。二本の耳は、いつもよりもピョンと立てた。我ながら上出来だ。
「やったぁ~! ウサギさんだぁ!!! へへへ」
チハルの大きなメガネの奥で、クリっとした瞳が細くなる。指でつまんだうさぎのリンゴに、チハルは今日一番の笑顔を見せた。
「なぁ、チハル。修二さん……あの世で幸子さんと逢えるかな?」
ハンバーグを目の前に、ご満悦なチハルに俺は問う。
「あたりまえですよ、それが絆というものです。おふたりの愛は本物でした。だから来世でも逢えますよ。これから先は、チフユさんの出番です。もう、死神の出番はありません……あっ! その前に、山本さんと一緒に幸子さんのお迎えに行かなくてはでした……へへへ。ねぇ、おじさん。このカタチ、おふたりのお気持ちのようですね」
そう言って、チハルはハンバーグを指さした♡

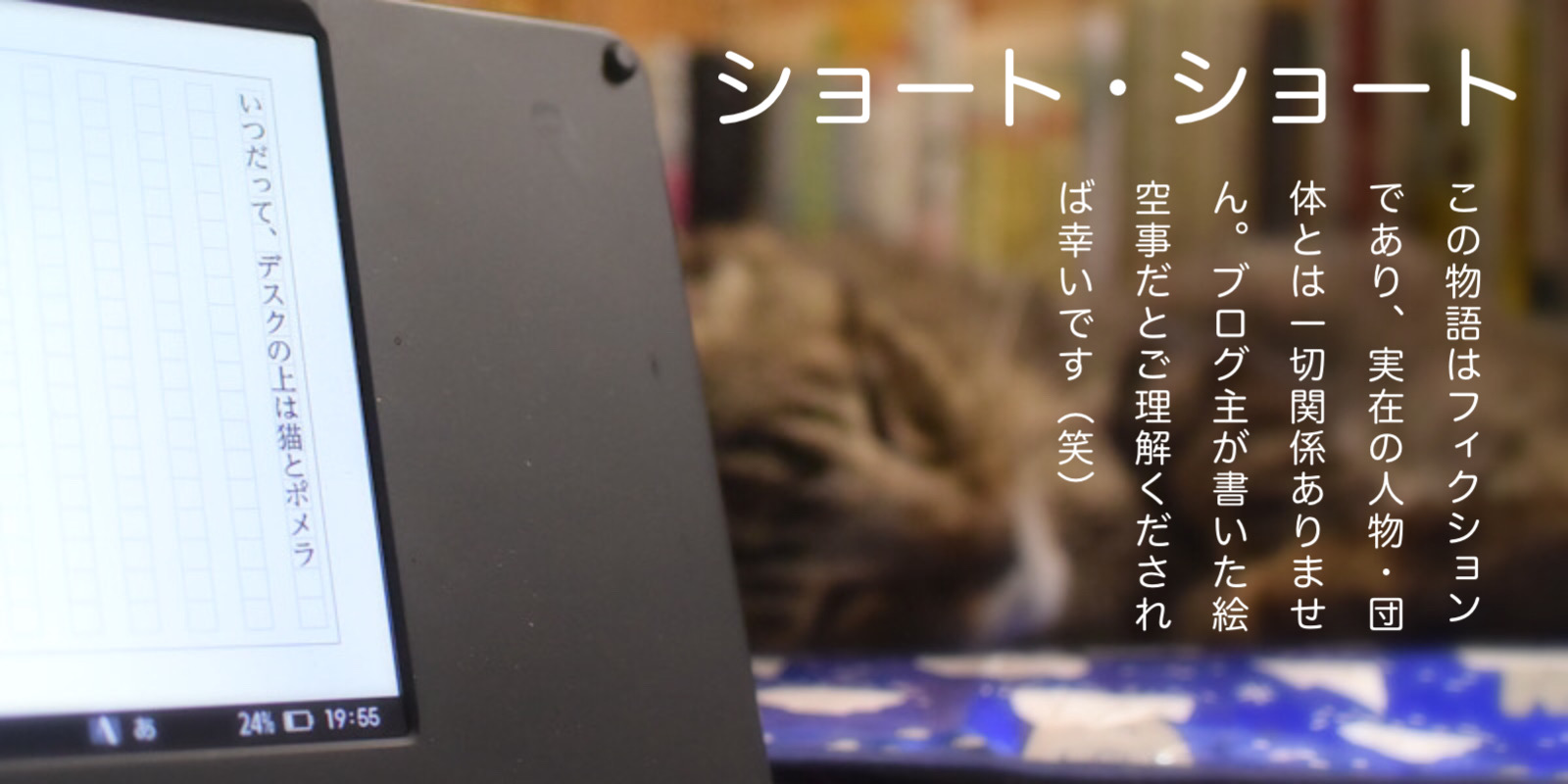

コメント