その男は、泣いていた。
夜の工場で、泣いていた。
誰もいない深夜作業を会社へ志願し、夜な夜な孤独な作業に勤しむ男がいた。けれど、男の涙を知る者は誰もいない……そう、いないはずであった。ある夜、残業帰りの事務員にそれを見られるまでは……。
「わたし、見ちゃったんです。深夜作業の男の子、泣きながら仕事してるんですよぉ。わたし、びっくりしちゃって……あれは、そう……むせび泣きでした。何て言ったらいいのかしら? 声すら掛けられませんでしたよぉ~」
それが、社長夫妻の耳に入る。
男はバイトである。これまでの真面目さを買われて正社員でもないのに、工場の鍵を預かっている身であった。そんな彼が泣きながら仕事をしている……それを知った社長夫妻は翌日、ふたりで彼の仕事ぶりを覗き見た。事務員の証言どおり、彼は涙を浮かべている。いつも笑顔の彼だからこそ、無縁だと思えた彼の涙にふたりが心配するのも当然である。
「ごめんよ、仕事中に」
口火を切ったのは奥さんであった。男は機械音に紛れた声に向かって振り返る。
「あ……奥さん、こんばんは。こんな遅くにどうしたんですか?」
慌てて男は涙を拭った。
「いやねぇ……アンタが泣きながら仕事をしてるって聞いたからさ……気になって、覗きにきたのさ。そしたら、ホントに泣いてるじゃないか? 声のひとつだって……ね? そうだろ? どうしたのよ、涙ぐんでさぁ……何か困ったことでもあるのかい?」
心配げに男に尋ねる。
「そうだよ。こいつの言うとおりだ。何か心配事でもあるのかい? 私らに相談できることなら、話を聞くよ。バイトだって、うちの会社で働いてもらっているんだ。これも何かの縁ってもんだろ? 遠慮しないで話してごらん」
社長も男が心配だった。
「あぁ……これは違いますよ。誤解です(笑) ほら……僕って、小説家志望じゃないですか? 作業をしながら小説を書いていたんです。頭の中で映画を観ている感じで。そしたら、感情が高ぶって。つい、涙が出ちゃうんですよ……僕。なんだか、ご心配をおかけしてすいません……」
男は頭を搔きながら、いつもどおりの笑顔を見せた。
「そうだったねぇ。アンタ、小説家になるんだったねぇ。そっか、そういうことか。でも、よかったよ。わたしゃ、心配で心配でさぁ。昨日は、おちおち眠れなかったよ」
男の笑顔に、奥さんは胸をなでおろした。
「あっそうか。君には応援してくれる彼女がいたね。彼女のためにも、凄い小説を書かないとな。いやいや、ホントに心配したんだぞ。でも、よかった。そこまで感情移入できるなら、きっと大作になるだろうな。本になったら、私らにも読ませてくれよ! わっはっはっは。でも、くれぐれも体を壊したり、怪我をしないようにしておくれよ」
「えぇ、まぁ……」
社長は励ますように、男の背中をポンと叩いた。
「そうかい、そうかい。だったら、芥川賞とか直木賞とか…折角なんだ、大物作家になっておくれよ。うちの商品を小説に盛り込んでくれても構わないからね。うちの商品、ドンドン宣伝しちゃってよ」
「えぇ、頑張ります……」
気の早い奥さんである。男は頭を下げるばかりであった。
「だったら、これは前祝い(笑)」
社長が男に封筒を手渡した。中には三万円が入れられている。
「いえ、こんな……受け取れません」
男は封筒の受け取りを拒んだ。
「まぁ、まぁ」
社長だって引き下がらない。そこは江戸っ子である。出した金は引っ込められないの一点張りだ。結局、男と押し問答になってしまった。
「だったら、こうしようよ」
奥さんが案を出す。
「アンタさぁ、このお金で彼女とデートに行くってのはどうかねぇ。悪いけど、どうせデートだって連れていってあげられないんだろ? これは、前祝いと小説の肥やし代ってことにして、受け取ってもらえないかい? アンタ、言ってたじゃないか? 『僕が作家になるのが彼女の夢なんです』って。今時、そんな彼女なんていやしないよ。だからさぁ、遊びに連れていっておやりよ……ね? デートのひとつもしておやりよ。だから、このお金は彼女のぶん(笑) あたしだって、この会社を旦那と立ち上げたころには…」
そう言って、奥さんは瞼に手を当てた。
「どう申していいのか……すんません……」
社長夫妻の温かさに、男は封筒を受け取り深々と頭を下げた。
「本になったら、読ませておくれよ」
「そうだねぇ、いの一番に読みたいねぇ」
そう言って、社長夫妻は工場を後にした。
その翌年。
仕事をしながら泣く男は、ついに作家デビューを果たした。そして、お世話になった社長夫妻の元へ男が挨拶に訪れた。
「これまで、本当にお世話になりました。おかげで僕は作家になれました。ありがとうございます。ご恩は一生、忘れません。これ、よかったら読んでください」
男は自分の小説を社長に手渡すと社長夫妻は笑顔を見せた。奥さんは、さっそく小説に目をとおした。小説の題名は、エンゲージメントリング。それは、主人公が彼女に指輪を渡すまでの物語。小説を読み終えた奥さんは、余韻に浸りながらあとがきのページをめくる。
「あ、あんた! これ……」
小説のあとがきに、あの夜の真実が語られていた。
「何てこった…」
───親愛なる君へ、この物語を捧ぐ。
社長夫妻は、最後一文に全てを察した。

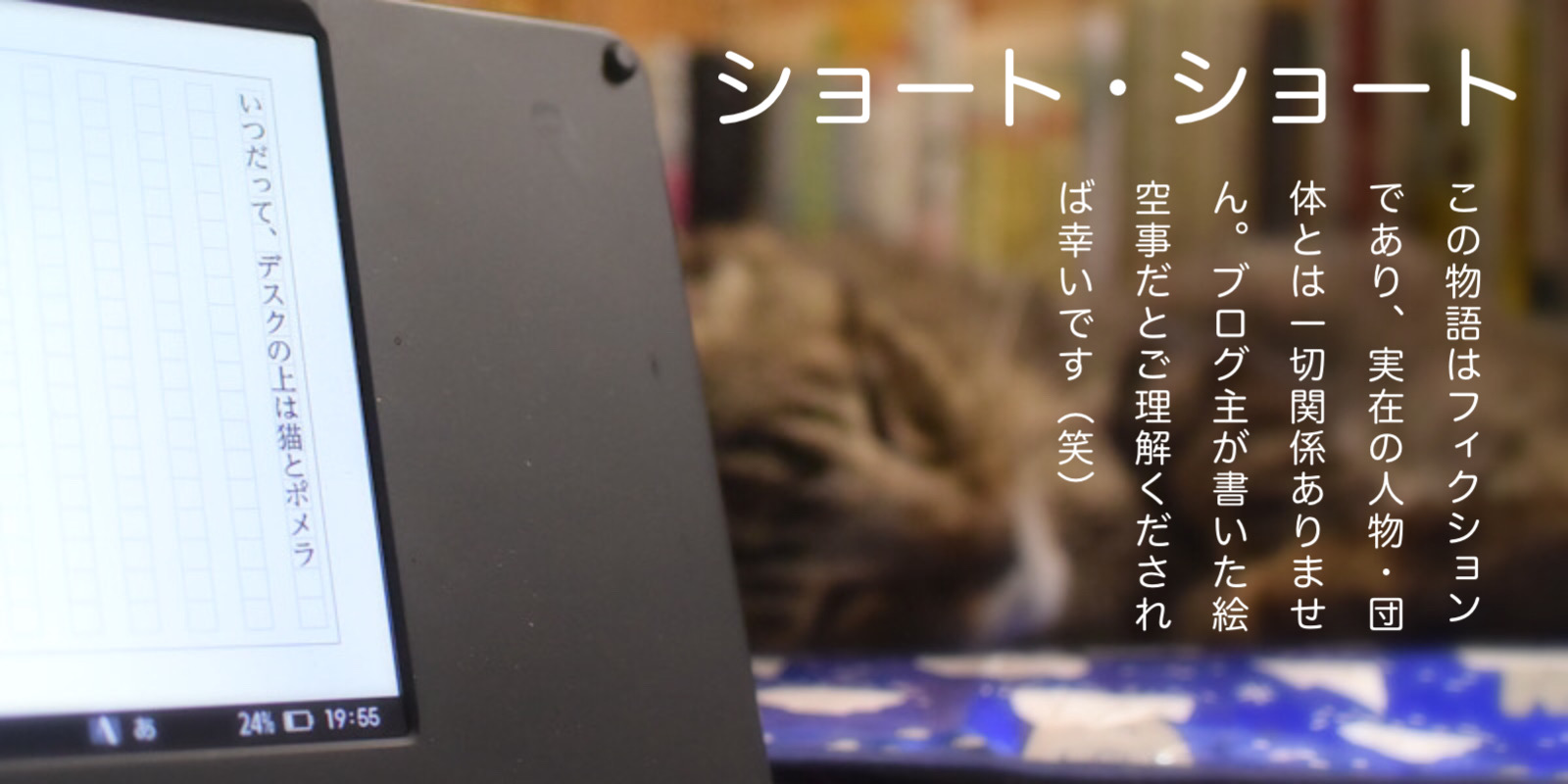

コメント