『邂逅』003ブログ
初夏の風が頬を撫でた。大きな黒目に萎縮した。それは、何から何まで見透かしたような目であった。『リンと呼んでね』そう、彼女は言った。けれど、オレの立場ではそうもいかない。残念ながら、オレは『リン姉さん』と呼ぶべき立ち位置であった。
「あ、はじめまして。オレ……いや、ボクの名前はアツシです。竹冠に馬と書きます。それと高一です。つい最近まで中学生でした。以後、お見知りおきを───リン先輩」
「あれれぇ。なんかねー、同級生くらいかなと思っていたのに。年下だったか。だったら、わたしがお姉さんね、今回は。じゃ、アツシ君だからアー君ね」
アー君は許す。けど今回って何?
この人の言い分が、たまに何言ってるのかよく分からなくなる。美人だけれど趣味は畑。機械いじりが得意な超優等生。人懐っこいのかデリカシーがないのか。それとも、懐が深いと言うべきか、ただの天然だと思うべきか。父さんは、どうして母さんと一緒になったのか。そんなことまで考えてしまった。
とはいえ、女子には目に見えない地雷があるらしい。少し前のネットニュースで話題になってた。余計なことは言わぬように。細心の注意を払いながら質問に答える。将来、何かの役に立つと思いながら。
「部活は?」
「やってないです」
「将来の夢は?」
「わかりません」
「ご飯食べてる?」
「まぁ、それなりに」
「ブログは書かないの?」
「あー。ボク、通信簿万年国語2なもんで。そういうのはやれません。それに今はVRどころか脳直結の時代です。今更ですよ、ブログだなんて(汗)」
「じゃ、書いて」
は?
リン先輩。オレの言ったこと、聞いてた? 通信簿は二段階評価じゃない。五段階評価だ。つまり、ケツから二番目のブービー賞。作文なんて書けませんて。オレにだってやりたいことは山ほどある。その中に作文の二文字は決してない。
「無理です、無駄です、できません」
「普通はね、無理ですとか、無駄ですとか、できませんのどれかだよ。そんなポンポンと語彙なんて出ないわ。だからこそ、アー君の文章が読みたいの。読んでみたいの。昨日、スイカ、あげたでしょ?」
この場でスイカを吐き戻そうかと本気で思った。謎の小包のつもりがブログの勧誘だなんて。そのうち、裏から怖いお兄さんでも出てきそうだ。けれど、リン先輩とオレとでは全てに於いて実力差があり過ぎる。何を言っても、はい、論破。そんな未来しか見えてこない。ない知恵を絞って断り文句を探し出す。
「あ、ボク、キーボードが打てません。ブログのシステムすら分からないッス。だからやれと言われてもですね……」
「知ってる。それ、嘘でしょ? わたしの目に狂いがなければ、その小包の中にあるポメラで何かを書いてみて。たぶんだけれど、指が勝手に動くはずよ。ブログの方はわたしが準備しておくから。日記でも書いて明日提出してね。ここで待ってる。それと、キーボードはね。見るんじゃないの、感じるものよ」
ブルース・リーかよ。
結局、小包の謎はあやふやにされ、このクラッシックなマシンで日記を書かされる羽目になった。きっとそう、リン先輩はオレで遊び始めたのだ。大人が子どもと遊ぶように、天才が凡才をイジくる遊びである。オレはリン先輩に完敗し、謎の小包を持って家路についた───晩飯が……美味くない。
「だったら、スマホじゃダメですか? フリックなら自信と勇気を持ってます」
「あら、可愛い。アー君って、そんな人だったかしら。もっと賢い人だったのに。でも大丈夫。わたしがついてる(笑)」
最後の足掻きも封じられた。完全に子ども扱いされたことが哀しかった。もっと賢い人だったって何だよ? もう面倒だ。バッくれようか。
その夜、オレはポメラを開くと、電源が自動で入った。すぐさま、オレの苦手な原稿用紙が表示された。首の周りが痒くなった。こういうのが、活字アレルギーの症状なのだろうな。首が痒い。
何も思いつかないまま、何も書けないでいるうちに、ポメラの電源が勝手に落ちた。電源ボタンを押すとすぐに起動する。それを何度か繰り返して気づく……キーボードにある筈の文字が消え掛かっていた。母音がない。「A」「I」「U」「E」「O」に該当するキーはボロボロでテカテカだった。これは無理。オレはやる気をなくしてそのまま夢の中に逃げ込んだ。誰が畑になんか行くもんか。
翌日、弁当を食べ終わると、雨がしとしと降り始めた。予報ではドンドン雲行きが悪くなるらしい。ラッキーである。リン先輩との約束も、雨と一緒に綺麗さっぱり流れるだろう。帰ったらネットゲームを楽しもか。作文なんてやってられね。
「ごめんください」
家でネトゲに勤しんでいると、土砂降りの雨の中、リン先輩の母親がやって来た。オレと会う約束をしてると言って、家を出たっきりらしい。まさかね、ドラマでもあるまいし。この天候でリン先輩がオレを待つなんてあり得ない。どうかしている。
───いつまでも私は待っています。
これは、五冊のファイルの中にあった一文である。それが頭の中を駆け抜けた。謎の小包、仮に二通の手紙と五冊のファイルを読破していたのなら。現実的ではないにせよ、リン先輩にはあり得る行動である。いずれにせよ行かないと。
オレはカッパを着込み、海水浴で使う大きな傘を担いでリン先輩の畑に向かった。リン先輩は、オレの担いだ傘よりも更に巨大な傘の下で座っていた。用意周到な女だった。折り畳み椅子まで用意している。その椅子に座ってノートに何かを書いていた。時折、双眼鏡で畑の何処かしらを見渡しながら。
───なーんだ、こんなのバカンスじゃん。アホらし。帰ってネトゲの続きしよ。ここからなら見つかりゃしない。オレは足を止めて右へ回れ。家に向かって舵を切った。
「そこの少年、止まりなさい!」
拡声器から聞こえた声は、紛れもなくリン先輩だった。振り返ると双眼鏡がオレを見ている。リン先輩は、どこまでも用意周到な女であった。
「きっと、来ると思ったわ」
貞子かよ? 逢いたくて、テレビから這い出して、オレに伝えたかったことがあるんですか? どうにでもなれである。逃げる気力すら失った。
「昨日は頑張りました。けれどポメラ、できませんでした。ごめんなさい」
「いいのよ、それで。いつまでもわたしは待っているから(笑)」
それ、引用か? 引用ですか? どうして、曾じいちゃんの過去に拘るのかが分からない。興味本位だとしても、誰もそこまでするワケがない。リン先輩に見えている世界とは何なのか? それを不思議に思い始めた。
「リン先輩。質問してもいいですか?」
「少年、ようやくやる気になったようね。何を聞かれても答えるわよ。早くわたしに言いなさい」
「先輩には、一体、何が見えているんですか?」
「いい質問だわ。その答え、知りたい? ねぇ、知りたくない? だったら、ポメラでブログを書いて。そうすれば、きっと答えが見えるから。それを、わたしは見たいの。できるだけ早く見てみたいの」
余計なことを言ってしまった。それは、目に見えない女子の地雷、否、起動スイッチと呼ぶべきか。やれるかどうか分からない。結局やれない気もしている。それでも、雨の中でオレを待つ、この人の望みを叶えてみたくなった。やらなきゃならない気がした。少しだけ、オレの世界線がズレた気がした。
その夜、オレはポメラと向かい合った。大真面目に向かい合った。ネットで調べてみると、このポメラDM250は二〇二二年製であることが判明した。物書き界隈では人気があったようである。
けれど、骨董品にも程がある。骨董品というよりも化石であった。オークションに出せばどれだけの値が付くのだろう? 曾じいちゃんには悪いのだけれど、今回の全てが終われば、速攻でオークションに売りに出そうと本気で思った。きっと、いい金になるに違いない。
だってそうでしょう? 今は西暦二〇七二年なのだから。
───邂逅という言葉がある。その意味は偶々うまく巡り逢うさま。オレは、偶々うまくこの時代に生まれ、偶々うまくこの場所に引っ越し、偶々うまく少女に声を掛けられた。でも、偶々うまく彼女の望みを叶えることはできなかった(最終話冒頭より)

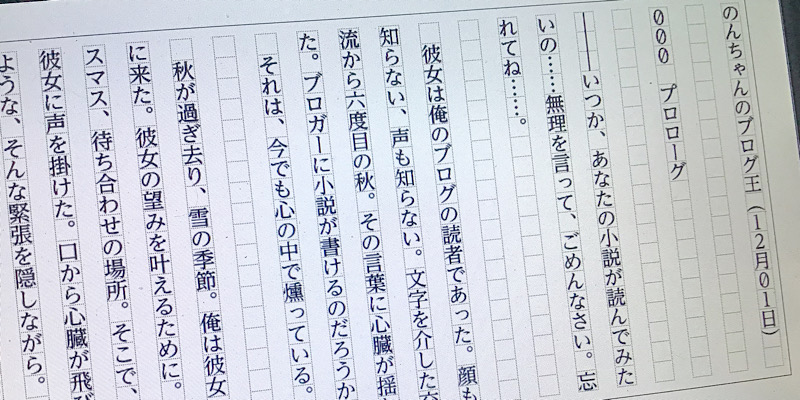





コメント