『邂逅』007お月様
夏休みの初め。妹が東大へ行くと宣言した。幼いながらに真っ直ぐな目をした宣言であった。兄として、止める理由が見つからない。あの脳天気だった妹を、リン先輩は半日で覚醒させてしまった。夏休みの宿題を早々に終わらせて、こっちが宿題に追われ始めたころになると、高一レベルを遙かに超えたドリルをこなし始めていた。一緒に夏休みの宿題を始めた妹の同い年は、いつしか妹の家庭教師になっていた。あれから図書館の自惚れやさんと未だ一度も連絡を取ってはいない。
「なんかねー、アー君に折り入ってお話があります」
出た、なんかねー。
リン先輩から折り入って? 心の警報が轟きパトランプが頭の中でグルグル回る。嫌でもオレは緊張していた。
「な、なんでございましょうか? リン先輩。いつも妹がお世話になっています」
「ねぇ、アー君。もう、リン先輩っての終わりにしない。なんかねー…わたし、年下だし。アー君のことね、いつも賢い人だなって思っているし。最近のブログ凄いし。わたし、学歴とかそういうので評価しないし。リンって呼び捨てでいいのに。そっちがいい」
「折り入ってって、それですか?」
「ほかにもあるけど、まずはこれから」
ニコリと微笑む顔が幼く見えた。でも、その先の言葉が怖い。何を言い出すのか覚悟しないと。
「じゃ、リ……リンさん」
「リンでいいってば」
「ああ、リン」
「何?」
「こっちが何?、なんだけど……」
もう、背中が汗でビショビショだ。
「アー君、あれから随分と本を読んだ? なんかねー、ブログを読んでいるとそれが分かるの。それはね、書く力と読む力が上がった証拠よ。曾お爺さんのファイルとお手紙。あらためて読んでみて。きっと、何かが見える筈だから。一度読んだから、曾お爺さんの願いは知っているでしょ? 今ならその気持ちが理解できる筈だから。ゆっくりでいいから、しっかりと読んで。噛みしめるように読み解いて。そしたら、わたしの所へ早く来てね」
それは何処?
こんな近くでリンの顔を見たことがあっただろうか。こんなに長い時間、リンの顔を見たことがあっただろうか。この子、まつげ、長っ! 黒目、デッか! ピンクの唇が艶々してる。真っ白な肌にこのパーツ群である。それが絶妙な位置関係で並んでいた。今更だけれど、ゾクッとするほどの美人であった。
人間の顔などコンマ数ミリの攻防戦だ。コンマ数ミリのズレで美人とそうじゃないのとに分かれる世界。きっちりと物差しで測ったように、左右対称に配置されたそれぞれのパーツ。これが黄金比というやつか。彼女の話そっちのけで、オレは、ただただリンの顔に見とれていた。いや、見惚れていた。
「アー君。ちゃんと聞いてる?」
「聞いてるよ、心に効いてる」
夏休みは、とっくに過ぎた。今は夏と冬の間、秋の気配を感じ始めたころである。夏休み、突如として東大へ行くと宣言した妹は、リン先生の指導で成績もうなぎ登り。一学期、中の中だった成績が、二学期の中間テストで全校でトップテン入りなんてどうかしている。クラスメイトから『いきなり秀才』という、団子の親戚のような称号まで手に入れた。もしかして、リンに改造手術でも施されたのか? そんな気にもなる。
さらに、いきなり秀才は宣言をする。リンと同じ高校へ行くのだそうだ。夏から秋までずっと妹のターンであった。これじゃ、兄貴の陰は薄くなるばかりだな。でも、嫌な気分にはならなかった。逆に誇らしくも思えた。一生、リンには頭が上がらないのだろうな。そう思った。
夕飯を食べ、風呂に入り、ブログを書いてから、あの小包を机に置いた。そして、ゆっくりと五冊のファイルに目を通し始めた。背中に双眼鏡の気配を感じながら。でもそれは、俺にはどうでもいいことだった。
小説とは人生の疑似体験である。読めば読むほど思うことがある。恋愛なんてどれも似たようなことばかりだなと。このファイルの中には曾爺ちゃんの恋バナが綴られている。曾爺ちゃんとあの人とのメールのやりとりが一冊。残りは、曾爺ちゃんに恋したあの人の知人と交わされたメールであった。二通の封筒の一通には、あの人からの直筆の手紙。もう一通には、爺ちゃんからのお願いごとが書かれている。
全部知ってる。
一度読んだから。だがしかし、中坊の思考回路は余りにも幼すぎた。真意を読み解くことができなかった。でも今は違う。その中に隠されたドラマは、これまで読み漁ったどんな小説よりもドラマであった。五十年前、こんなことが実際にあっただなんて。きっと、誰に語っても信じてはもらえないだろう。
───オレはその夜、人を好きになる重さを学んだ。
そのファイルを読み終えると、深夜にリンからのメールが届いた。明朝、芋掘りをしようとのお誘いだった。結局、寝たのかどうだか分からないまま、言われるがまま畑に行くと、作業着姿のリンがいた。この少女の辞書には睡眠の二文字はないらしい。そして、オレに制服姿を見せる気もないらしい。
「アー君、おはよう」
「おはよう、リン」
互いに慣れぬ『リン』の響きが初々しい。オレらは、それ以上の言葉を交わすことなく芋掘り大会が幕を開けた。あの朝、赤いテントの前でオレの背中を叩いた爺さんが、オレに軽く手を振り満面の笑顔で通り過ぎた。カッケー大人だ。将来オレもあんなジジイになりたいと思った。それにしても、やり始めると芋掘り楽しい。穴を掘るたび良い感じのサツマイモがゴロゴロと出てきた。
「楽しいねぇ」
リンは目を細めてオレを見た。これはもう、そういうことじゃないですか? もはや、これはデートと言っても過言じゃないですか。気持ちが一気に引き込まれる。それでも最後のブレーキは外せなかった。そう、学歴の差である。いずれ、彼女は東大へ行くのだろう。もしかしたら、マサチューセッツ工科大学とかに行くのかもしれない。いずれにせよ、高嶺の花だ。ぬか喜びも程々にである。
「ちゃんと読めたみたいだね。目が真っ赤だもの。わたしと同じように。でね、もう一度、同じ質問するね。わたしと会ったことなぁーい? 例えば前世で」
「ない」
即答した。
ロマンチックな場面だけれど、申し訳ないがそれはない。そもそも輪廻転生なんて信じてもいない。死んだらね、それで終わりなんだよ人間は。だから、この一件はオレ独りで終わらせよう。リンを巻き込んではイケない気がした。その前に、ひとつだけ質問をしよう。これが最後の質問のつもりだった。
「リンは、輪廻転生っての、信じているの? オレは信じていないけど」
「あー、オレって言った。年上だと勘違い中はボクだったのに、オレに戻ったぁ。」
ケラケラと、リンは無邪気に笑って見せた。少し涙ぐんだような顔をして。
「なんかねー、わたしもね、信じてないの。輪廻転生。でもね、わたしは小学三年から、ずっと自分を研究してきたの」
何を言い始めたのか理解できない。自分を研究って……。
「小学三年生のころ、何だか思ったの。会わないといけない人がいるって。そのために生まれてきたって。漠然と思ったの。でね、前世の記憶とかって言うじゃない。五歳ごろまで前世の記憶が残るって。でね、ママにお願いしたの。わたしの記録、全部見せてって。なんかねー、ママはね、昔は生粋の動画配信者だったの。結構、人気があったそうよ。だから、わたしが生まれてからの動画が膨大に残っていたの。わたしは、小学生時代をね、自分の動画の研究に充てたんだ。そのころは、中学の勉強は既に習得してたから暇だったし」
それを暇と呼ぶのか……。天才の思考がさっぱり分からん。
「動画を見続けて思ったの。月を見せると赤ちゃんのわたしは喜ぶの。その理由が分からなかった。なんかねー、最初に覚えた言葉は「お月様」なの。二歳のころ、お月様に会いたいって頻繁に口に出していたの。満月を見て泣いてる動画もあったわ。あと、サヨリちゃんとキジトラさんって言っていたの。ねぇ、アー君。わたしの口癖知ってる?」
「なんかねー……えっ?」
オレは息を飲んだ。あの人の口癖も『なんかねー』であった。それでもオレの心は抵抗し続けた。輪廻転生などある筈がないと。

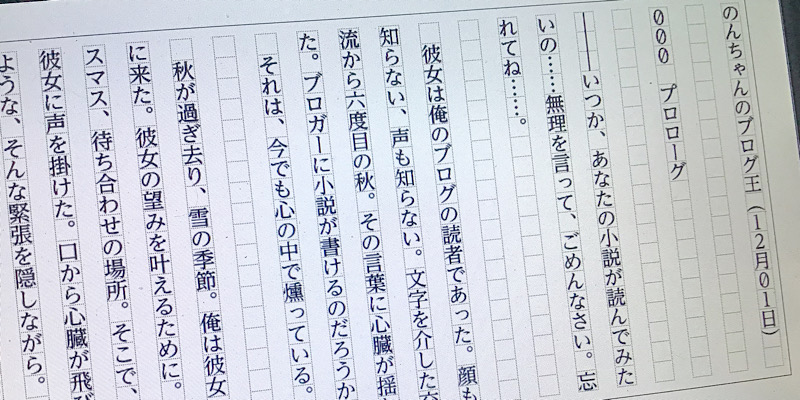
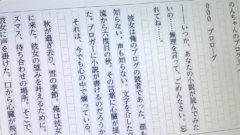
コメント