『邂逅』012邂逅
邂逅という言葉がある。その意味は偶々うまく巡り逢うさま。オレは、偶々うまくこの時代に生まれ、偶々うまくこの場所に引っ越し、偶々うまく少女に声を掛けられた。でも、偶々うまく彼女の望みを叶えることはできなかった。
リンと出会った次の夏、オレたちは四国にいた。
発端は昼飯である。リンが高三、妹が中三の春休みの出来事。勉強中、妹がリンに話しかける。
「リンの姉御様。今日のお昼はナニ食べる?」
それはいつものことである。無料で勉強を教えてもらっているのだ。そのお陰で妹の成績はグングン上がり志望校も射程圏に入った。妹にとってリンは大切な恩師である。だから、ステーキだろうが、寿司だろうが、リンが何を注文しても母が許す。
「なんかねー、本場の讃岐うどんが食べてみたいの」
「えーーーーーー、そんなのでいいのぉ? お母さんに作ってもらう? 讃岐の女は、うどんが打ててナンボです(笑)」
「それはダメ! 讃岐うどんは讃岐で食べないと讃岐うどんとは呼べないわ。でも遠いから出前を取っても麺が伸びちゃうね(笑) それでもね、いつか本場の讃岐うどんが食べてみたいなぁ~」
リンは寂し気な顔でそう言った。妹は母親に相談し、母親がリンのママに相談した。その結果、我が家の墓参りにリンを同行させることに決まったのだ。帰省当日の朝までオレはその事実を知らされていなかった。オレの家族とリンの家族。その全員が知る中で、オレだけが知らなかったことになる。帰省当日の朝、黄色いワンピースに身を包んだ少女がいた。呆気にとられたオレに妹が耳打ちをする。
「兄貴殿、舞台は用意したぞよ。しっかりと、お励みなされ(笑)」
ませガキが。
香川さん辺りじゃ、そろそろうどん打ってるころ。明石海峡大橋の上でリンがオレに話しかけた。
「あれ、やるんでしょ?」
「そのつもりだ」
リンの言う「あれ」とは、散骨である。小包の中の曾爺ちゃんからの願いごとがそれであった。
───大切な人が待っている。もし、この箱を見つけた人がいたら、海に骨をまいてほしい。
ただそれだけが書かれていた。彼女の亡骸は海に戻された。だから、己れの一部でもいいから一緒になりたいのだろう。とはいえ、願いが願いである。高校生のオレには対処できない頼みであった。親にも相談できない、誰にも言えない、でも願いを叶えてやりたい。そのタイミングでの帰省である。これはもう、やれってことで構わないだろ? 我が家の墓を守る寺。住職の息子は同級生の山田であった。事前に要望を伝えたけれど、山田からの返事は一向になかった。もしもダメなら墓を荒そう。身を捨ててこそ浮かぶ背瀬もあれだ。その覚悟での帰省であった。
静岡から香川までの移動時間は車で約四時間。二〇六〇年代、高速道路の速度規制が緩和された。自動運転なら時速二〇〇キロにセットして、インターチェンジまでなら寝ていてもAIが勝手に連れていってくれる。つまり、日帰りも十分可能。けれど、妹の悪巧み、否、強い要望で一泊二日の日程が組まれた。親戚らにはリンを妹の同級生として紹介するらしい。まぁ、それが正解だろう。
予定通り叔父の家に到着し、挨拶を交わしてオレは寺に向かった。妹とリンは連れだって、我が家の行きつけのうどん屋へ出掛けた。寺の境内に入ると山田が待っていた。
「よう、久しぶり(笑) 随分なお願いだな。ご先祖様の骨をくれだって? 先ずは、どういった了見なのか聞かせてほしい。お前のおっちゃんに、今日、こっちに戻ってくるって聞いたから、朝からずっと待ってたんだ。うちの親父に見つかると、とんでもないことになるからな」
「返事がないからダメかと思った。でも山田、そんなことが可能なのか?」
「しーっ。声がデケぇよ。下手すりゃお縄の話だぜ(笑)」
オレは一部始終を彼に告げた。
「信じられん話だけれど、俺は篤を信じるよ。それくらいお安いご用だ。今から墓へ行こう。ものの3分で終わる話だ。あ、それと、この話。俺が坊主になったらお説法で使わせてもらうからな(笑)」
使いもしないくせに。でも、ありがとな。
オレたちは墓から曾爺ちゃんの骨を盗み出し、人知れずその場で別れた。
「山田、無理を言ってすまんかった。このお礼はきっとするから」
そう言い残し、オレは叔父の家に戻った。丁度、リンと妹もうどんを満喫して帰ったところだった。
「旨かったか、讃岐うどんは?」
「うん(笑)」
いい顔だ。嘘のない笑顔だった。
「で、そっちはどうだった?」
オレはポッケを指でさした。天を仰ぐと、真っ青な空に大きな雲が浮かんでいた。
「そろそろ行く?」
「先祖供養に行きますか(笑) 海への途中に凄いのがあるから、先ずはそっちを案内するよ」
「凄いのって……怖いのはダメよ」
「リンなら一目で理解するよ。曾爺ちゃんの本気をね」
海への途中にひまわり畑がある。十メートル四方の小さな畑。それは曾爺ちゃんの畑である。あの人が旅立った春、曾爺ちゃんは畑にひまわりのタネを蒔いた。祖父も父親も畑には興味がない。長年放置された畑は夏になると無数のひまわりで覆い尽くされた。いつしか曾爺ちゃんのひまわり畑は、この地域で夏の風物詩となっていた。多くのカップルがひまわり目当てに訪れた。大輪のひまわりに隠された物語など誰も知らずに。
「……」
リンのリアクションはゼロだった。ただ黙ってひまわりを見つめているだけである。オレは声を掛けるのを躊躇った。話しかけるのが野暮に思えた。この場はそっとするべきだ。オレは被っていた麦わら帽子をリンの頭にそっと乗せた。
「この道を真っ直ぐ行くと海に出る。オレは堤防の先で待ってるから。曾爺ちゃんとゆっくり話してくるといいよ」
リンはコクリと頷いた。
邂逅という言葉がある。偶々うまく巡り逢う意である。五十年前、広大なネットの中から、曾爺ちゃんのブログと偶々うまく巡り逢い、彼に惹かれて恋に落ちた女性がいた。それは紛れもない事実であった。そして生まれ変わりのリンの存在も紛れもない事実である。でもこのパズルは完成しない。ひとつのパーツが見つからない。曾爺ちゃんの生まれ変わりは何処にいる? オレたちは、雲をつかむように半年以上も探し続けた。結局、何も分からなかった。『ブログ王』までたどり着き、そこから何ひとつ進展なしだ。
───だからもう潮時だ。
なぁ、曾爺ちゃん。オレ、頭悪くてごめんな。馬鹿でごめん。リンもがんばってくれたけれど、曾爺ちゃんの生まれ変わり、見つけられんかった。もっと、こう、分かり易く生まれ変わってくれたら、いいのに。オレ、一旦、探すの諦めるわ。オレ、もうすぐ受験なんだ。でも、行ける大学が見つからないんだ、アホだから。リンだって、来年、東大に入ればオレと会うこともないだろう。でも、曾爺ちゃんの願いだけは叶えるからな。それで許してほしいんだ。その代わり、リンをずっと見守るから。あの子が素敵な彼氏と出逢う日まで。それで勘弁してくれよな。
防波堤に腰を下ろし、オレはキラキラ光る波を見ていた。曾爺ちゃんはうまくあの人の所へ行けるだろうか。海は繋がっているから、そのうちきっと会えるだろう。何年かかっても、偶々うまく巡り逢ってくれたらそれでいい。
「アー君、お待たせ」
リンの目は赤かった。少し泣いてきたのだろう。オレは曾爺ちゃんの骨粉を海にまいた。リンはオレの後ろでそれを見ていた。これでお役御免だ。あの小包は押し入れの奥に仕舞い込もう。リンへの想いと一緒に。
「なんかねー、わたし、東大やめて地元の大学に行くことにしたの。昨日、担任の先生に伝えたの。今ごろ、ママとお話してるでしょうね」
でしょうね……って何だよ。
「何言ってんの、馬鹿じゃないの。東大行けるんだから行っとけよ。上級国民になって幸せ掴めよ。オレとなんかいても後悔するぞ。世の中はな、恋愛感情なんかで動いちゃいない。損得勘定で動いているんだ」
「でもねー、わたし生まれ変わりだから。生まれた目的、東大じゃないから。アー君の近くにずっといたいの。だから、明日から勉強教えてあげるね。同じ大学、一緒に行こ(笑)」
こいつ、マジだ。久しぶりに見た意地悪な笑顔。
「アホか……」
波の音がふたりを包んだ。
海からの帰り道、もう一度ひまわり畑の前を通る。リンは畑の隅っこを指さした。
「ねぇ、ねぇ。あの中に雷電あるかも。小説にも描写があったわ」
「あの人が好きだと言ったから、いつでも遊びに来れるように…。プラモを作って畑に飾ったって戦闘機のことか? あ、そっか。もし事実なら、リンにとっても大切なものだよな。よし、あったら持ってくる」
畑に咲いたひまわりは大量のミツバチを集めていた。その中を通ってロッカーの中を探すのだ。ミツバチとはいえ、刺されたら痛いんだろうな。ひまわりの花をよく見るとうじゃうじゃだぁ。こりゃ、決死の覚悟が必要だな…。
「アー君、気をつけてね」
「わかってる」
「ひまわりの茎、折っちゃダメだよ」
そっちかーい!
オレはひまわりを傷めぬように、ヘンテコな姿勢でロッカーにたどり着いた。さすが半世紀モノである、ボロボロだ。引き違い戸を動かすと、手を掛けた引き戸がボロリと崩れた。なんかごめん、もうコレ直らん。ロッカーの中に雷電を見つけた。それを手に取り畑を抜ける。そして、リンに手渡した。
「これ持って帰れ。曾爺ちゃんからのお土産だ」
リンは両手で雷電を受け取り、大切そうに抱えて歩いた。これでオレの目的は全て終わった。さぁ、帰ろう。
「リンの姉御ぉ~、スイカ切ったどぉー」
妹が大声でオレたちを呼んだ。後のことはスイカを食ってから考えよう。オレとリンは手を振る妹の方へと足を進めた。妹の後方一メートル向こう側。切ったスイカをお盆に乗せてオレに目配せする母がいた。我が親ながら悪い目をしている。
「うぁーーーーー雷電。びっくりポン」
こっちがポンだよ。雷電を見て興奮しているのは母であった。その理由は知らんけど。
「これ、どっから持ってきたの? アンタの雷電は本家の納屋にあるからね。でも、これ、雷電だよね、雷電。懐かしいなぁ、ねぇ、あっちゃん(笑)」
母親が雷電を見て懐かしむ要素がまるで分からん。元カレに、そんな趣味でもあったんか?
「何でこの戦闘機の名前を知っているの?」
この疑問は当然である。このプラモを戦闘機と理解しても、普通なら零戦だろ?
「あんた、何個、買わされたと思ってるのよ。『雷電がー、雷電がー』って、おもちゃ屋の前で大泣きしたの忘れたの? そんなの覚えてないのに忘れられないわよ」
「買わされた?」
リンがオレの腕をギュッと掴んだ。その顔は何かを察した表情であった。大きな黒目がキラキラしている。顔に嬉しいと書いてある。オレは斉藤から受け取ったメッセージを思い出していた。
───人は前世の記憶を持って生まれ出る。二歳ごろから前世を語り、五歳のころにその記憶の全てを失う。
リンに内緒で得ていた情報である。
「あのね、あんたが二歳くらいのころだったかしら。異常に雷電に興味を示してね。誕生日とか、クリスマスとか……プレゼントは雷電ばっかり。でも、プラモでしょ? 後でお父さんに作ってもらっていたのよ。それからプラモに味をしめて、あの人、今じゃ立派なガンプラおたくよ。五歳くらいまで続いたかしら……」
全く記憶に残っていない。でも、その雷電は何処に行った? 捨てたのか?
「あんたが五歳のころ、あんたは、おもちゃ箱を本家に担いで持っていったの。で、納屋の奥に置いてそのまま帰ろうとしたの。母さんは、ちょっ、ちょっ、ちょっ、よ。だってそうでしょう? 仮にも、お父さんのお兄さんの家よ。勝手に納屋におもちゃを置いて帰ろうとするんだもの。そりゃ、私だって普通に慌てるわよ。で、理由を聞いたのよ。そしたら……」
おい、それからどうした? 続きはよ。
「そしたらね、あんたこう言うのよ。『これはのんのの乗る雷電。僕はもうすぐ忘れてしまう。だから、のんのを見つけたら、また、ここに取りに来るの。のんのは海にいたけど、今はこっちに来てるから』だって。あんた、のんのが口癖だったし、一度言い始めるとテコでも動かないから。そこ、誰に似たのかねぇ……。だから、お義兄さんに頼んで、おもちゃ箱を置かせてもらったのよ。私も忘れていたけどね(汗)。ところで、のんのって、何? あら、ちょっと。アナタたち、スイカは?」
スイカどころではなかった。
オレたちは探し求めた答えを見つけた。『のんの』とはあの人の呼び名である。オレの行き先は決まってる。本家の納屋の屋根裏だ。叔父さんならきっとそこに仕舞うだろう。納屋に駆け込み、梯子を立て、屋根裏を覗き込む。真っ暗だ。スマホを翳して辺りを見渡す。あった、あれだ。
リンゴ箱ほどのおもちゃ箱。それを下ろしてフタを見ると、黒いクレヨンで大きく何かが書いてある。
『のんの の らいでん』
下手くそな大きな文字が書かれていた。その勢いは、『書く』というより『描く』であった。オレはリンの息が整うのを待った。走って来たのだから仕方ない。そしてふたりでフタを開いた。中に無数の雷電があった。
これが幼きオレからのオレたちへの回答である。あのまほろばで、リンが言ったひまわりの花言葉。もし雷電に花言葉があるのなら、それはきっと同じだとオレは思った。
───何度生まれ変わっても君を愛す
短編小説『邂逅』完。

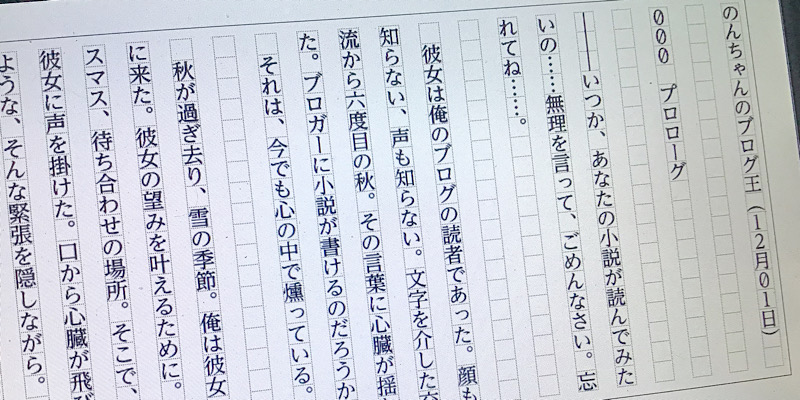
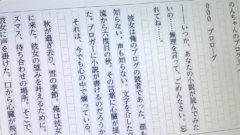
コメント
読んだ直後はすぐに言葉がみつからなかったです。素晴らしい小説を読ませていただき、ありがとうございました。偶々うまく、このブログと出会って良かったです。ところでアー君、可愛い女の子が「アー君の近くにずっといたいの」と、実質的には告ってるようなものなのに「アホか…」の一言で返すところ、アー君らしいですね。なんか男前だなぁ~。
最後まで読んで頂きありがとうございます(笑)。無事に初めての短編小説を書き終える事が出来ました。ほんと、偶々の繋がりが大き過ぎて、でも、その集大成を込める事が出来た想いです。次はこれ以上、そう思うと小説家って人は過酷ですね(汗)。
ヤバい。
語彙力皆無になる。
ヤバいよヤバいよ。
凄い読後感
ありがとうございます。
それだけでホッとしました。
次への糧にします(笑)。